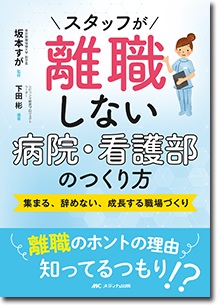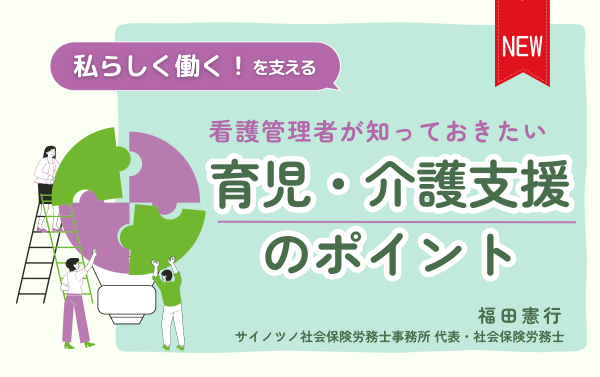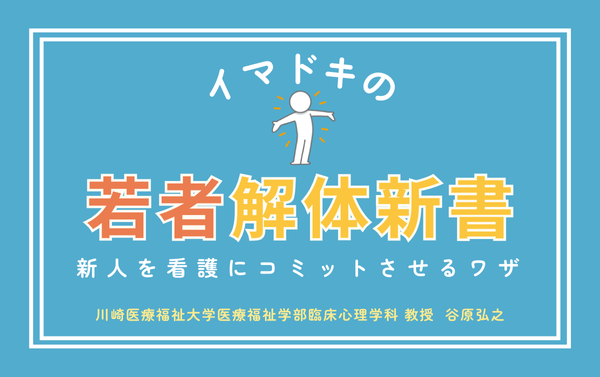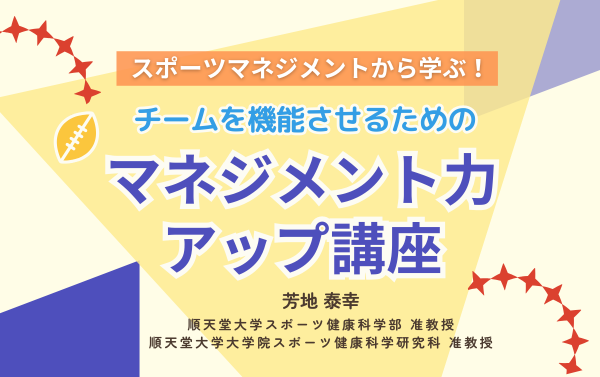『つながる看護管理 VOICE』第3回目アンケート結果
「どうすれば辞めずに続けてもらえるのか」。
現場の声に耳をすましながら、日々、離職防止に取り組んでいる看護管理者たち。
今回のアンケートでは、離職が起きる背景や、現場にある本音、そして辞めずにすんだ工夫について尋ねました。
「辞めたい」と「続けられた」の間にある、小さな気づきを、ここで共有します。
■ 9割が離職を「課題」と認識
今回のアンケートでは、92%の看護管理者が「非常に深刻」または「ある程度の課題」として、看護師の離職を問題視していました。
「特に問題はない」は皆無で、「少しずつ改善している」もわずか2%。これは、病院や施設にとって看護師の定着がいかに大きな課題となっているかを示すものです。
とくに人手不足や夜勤体制の維持が難しい現場では、「一人の退職が連鎖する」状況も少なくありません。
| 直近1年間で、あなたの職場における看護師の離職状況について | 人 | 割合 |
|---|---|---|
| 1: 非常に深刻な課題だ | 21 | 45% |
| 2: ある程度課題だ | 22 | 47% |
| 3: どちらともいえない/判断が難しい | 3 | 6% |
| 4: 少しずつ改善している | 1 | 2% |
| 5: 特に問題はない | 0 | 0% |
*回答数47件
■ やめたい理由、その背景にあるもの
離職理由として多く挙げられたのは、
- 給与・待遇への不満
- 人間関係の悩み
- ワークライフバランスの課題 など
でした。
| 離職する理由 (複数選択可) | 人 | 割合 |
|---|---|---|
| A: 給与・待遇への不満 | 30 | 64% |
| B: ワークライフバランスの課題(長時間労働、夜勤負担、休暇の取りにくさなど) | 23 | 49% |
| C: 人間関係の悩み(上司、同僚、他職種との関係など) | 26 | 55% |
| D: 仕事内容への不満(やりがいを感じない、スキルアップの機会がないなど) | 17 | 36% |
| E: キャリアパスが見えない | 7 | 15% |
| F: ハラスメント(パワハラ、セクハラ、ペイハラなど) | 6 | 13% |
| G: 教育・研修体制への不満 | 5 | 11% |
| H: 健康上の問題 | 9 | 19% |
| I: 自分の適性・能力への不安 | 11 | 23% |
| J: 結婚・出産・育児・介護などライフイベントとの両立困難 | 19 | 40% |
| K: 病院・法人の経営状況への不安 | 6 | 13% |
| L: 他施設・他分野への関心・転職 | 21 | 45% |
| M: その他 | 3 | 6% |
*複数回答のため、合計は100%を超える(以下同じ)
M: その他
| 離職する理由 (自由記述) |
|---|
|
・高齢化 ・日々の勤務量が多いことに加えて、委員会活動に時間を費やす。超過勤務でしか、監査や議事録作成、作業などの委員会活動ができない ・医師からの言葉の暴力。アホやらバカを平気で言う医師がいる。また、医師から無理難題な要求(例えば外来診察中、師長のPHSに電話が入り「次の患者さん呼んで」や、診察室のクーラーの風に対して「風が当たらないように調整して」など)を言ってくる。外来診察時はご自身でマイクで呼んで欲しい事を伝えても聞いてもらえない。ほかにも、診察依頼をしたとき「何で僕に言うの、もう1人の先生に診てもらってよ」と言われ、ほかの医師に依頼すると、「この患者は僕の担当じゃないよ、みれない」と言い、患者を診てもらえない。この現状を院長や副院長に伝えても、そこは看護師がうまくやってよ、と言い相手にしてもらえない。上記のことが続き、外来看護師が疲弊し大量に退職した。また病棟看護師も医師との対応に疲弊し、退職する人が後を経たない。この現状をみて副院長は、「辞めたい人は辞めたらいいですよ」と言い、副院長についてこない人は知りません、のスタイル |
■特にいま困っている(解決したい)課題
離職理由のなかで、看護管理者が「特にいま困っている」と感じている声からは、取り組みにおける葛藤や矛盾が浮かび上がってきました。
たとえば、過重な業務に加え、他職種とタスクを分担できない体制。人手不足のなかで、看護師が疲弊し、メンタル不調者は増えるが、管理者が少なくフォローし切れない窮状。
また、「責任のある仕事はしたくない」といったキャリア層の価値観の多様化や、「夜勤者ばかりが報われない」という不公平感も、現場の士気を下げる要因に。
さらには、経営層の理解不足、看護部長への責任転嫁など、職場風土そのものが離職を後押ししているという声も。
働き方の調整が叶わない、上司との方向性がかみ合わない、育成に時間をかけても結果につながらない―こうした積み重ねが、気力や自信を奪っていく過程が見えてきました。
どの声も、「誰かが悪い」では片付けられない、構造的な課題と現場の想いのギャップを映し出しています。
| 離職する理由の中で、特にいま困っている(解決したい)課題 (自由記述) |
|---|
|
・田舎の回復期病院で、専門職種の人員不足+看護師不足なのに、タスクが増えるのは看護師だけ。タスクシフト、タスクシェアがまったく進んでいないため、看護師は疲弊し離職につながっている ・ほかの施設を知らずに、隣の芝が青くみえる状態 ・承認欲求は高いわりに、スキルアップした時点で責任のある業務に就きたくない中間層がいる ・休暇が一番多くて地域平均以上の給与が欲しい ・外来勤務のベテラン看護師の離職。業務負担で疲弊しているというが、他部署より残業時間は少なく、疲弊の尺度が理解できない ・夜勤回数が増える、体調崩すのサイクルから逃れられない ・ライフワークバランス ・疲れたと言われて辞められるのはとてもキツイです。看護師数は足りているのですが、夜勤ができる看護師が7割で、回数が多く疲弊しています。育児には手厚いですが、頑張っている夜勤者へ手当をあげられないことが一番の課題です ・「長時間労働」「忙しすぎる」と不満が多い。病院経営としては、急性期を辞めたので看護師は、要らないと思っている。ただ単に、人がいなくて忙しいと思っている。解決策をスタッフに周知するには、音声入力などを導入するなどしなくては納得いかないと思う ・超過勤務、業務の煩雑さ ・看護師の退職に対して、「看護部の問題、看護部長の采配が足りない」と事務長から言われ、組織的に取り組んでもらえないこと。また事務長から、「看護師が辞めるのは看護部長に不備があるから今度からそこにも介入します」と言われ、看護部長自身のマネジメントに苦言を呈し、看護部長の自尊心は傷つけられている。はたから見ても、耐え難い状況。院長、副院長、事務長、看護部長の上層部が手を取り合い支え合い、の関係性が望ましいが、今は相手を批判するだけのように見える ・キャリアアップのために田舎を離れていくこと ・ワークライフバランスをとり、本人の望んだ勤務形態に変更することが困難で退職となった ・メンタル低下での理事の離職や病休 ・地域密着病院は慢性期ののんびりした印象らしく、急性期で忙しい状況を目の当たりにしてこんなはずじゃなかったといわれるときがあります ・パートが常勤になるためにどう介入すればよいか ・時間外勤務の短縮に取り組んでタスクシフト、タスクシェアをするにも、他職種や委託業者も人員不足 ・入職したばかりの人が病んでしまう。管理職が足りなくフォローしきれていない。中途採用の人がやりがいを感じられない職場となっている可能性 ・組織が成熟していない。体制を整えられない ・メンタル面の不調を抱えるスタッフが多い。病気休暇期間が長い ・倫理やACPを進めるうえで、上司-スタッフ間の意見の違いがある。利用者の生活や人生のあり方について意見がぶつかり同じ方向にすすめない ・管理職の退職。院内の教育や体制などから負担を感じ退職されると正直、残るスタッフも不安になる。目指すナースが辞めることで、周りのスタッフのモチベーション低下につながっているように感じる ・5年未満の職員の離職。ライフイベント以外に、急性期病院が自分に合わない、指導体制の不均衡(忙しい業務で指導の丁寧さ不足とそれに耐えられない新人など)の理由となっている ・仕事がキツイとの理由が多いが、ほかの病院の話を聞いてもさほど忙しくない ・看護師としての適応が厳しいスタッフを活用するために、多大な時間をかけて育成するが、自身で看護師には向いていなかったと判断し、一人立ちを目前に退職となる。就職面接時点での判断は難しいのか。離職となれば、全て現場の管理者の責任となっている。離職率何%と数字だけを見て評価される。面接官の面接スキルが低い ・職場において、ムードメーカーの退職により、周囲が引っ張られるように退職が続いていること ・近隣の病院の給与相場に比べると2万円程度低く、また職員の多くが望んでいる半日有給などの導入がシステム上対応できない |
■実際に行われている離職防止の取り組み
離職防止の取り組みとして多く挙げられたのは、
- 「勤務体制の柔軟化」
- 「eラーニングなど教育体制の整備」
- 「キャリア開発支援」
- 「定期的な面談・カウンセリング」 など
ストレスチェックやメンタルヘルスケア、スタッフの再雇用、タスクシフト/シェアなども3割以上が実施しており、現場ではどの施設も複数の取り組みを行っています。
| 看護師の離職防止のために行っている取り組み (複数選択可) | 人 | 割合 |
|---|---|---|
| A: 給与・福利厚生の見直し | 10 | 21% |
| B: 勤務体制の柔軟化(時短勤務、日勤常勤、変則勤務など) | 32 | 68% |
| C: メンター制度、プリセプター制度の強化 | 14 | 30% |
| D: キャリア開発支援(研修機会の充実、資格取得支援など) | 23 | 49% |
| E: 管理職による定期的な面談・カウンセリング | 23 | 49% |
| F: ストレスチェック、メンタルヘルスケアの充実 | 18 | 38% |
| G: ハラスメント対策の強化 | 14 | 30% |
| H: ワークエンゲージメント向上のための施策(感謝の表現、承認の機会など) | 10 | 21% |
| I: タスクシフト/シェア、看護補助者の増員など業務負担軽減策 | 16 | 34% |
| J: ITツールの導入による業務 | 11 | 23% |
| K: eラーニングなど教育体制の整備 | 26 | 55% |
| L: 離職したスタッフの再雇用制度 | 18 | 38% |
| M: その他 | 4 | 9% |
自由記述には、具体的な取り組みの例も多数寄せられました。
| 取り組みの成功例 (自由記述) |
|---|
|
・就職後、1週目、3週目、3ヵ月目、と面談をしている。面談することで病棟の課題が見え、早めに対策をとることができている ・当院に必要とする人材を明確にし、その文化にあった人材を採用する ・漠然とした退職理由のときはとにかく対話。離職希望のスタッフの話を聴き、必要な人であることを伝える ・中途採用者の人にもリフレッシュ研修に参加してもらい違う病棟の同期との連携を図ったのはよかった。4月の合同研修では中途採用者も当院のマニュアルや物品を知ってもらうために、全部の研修に参加してもらった ・看護を実感してもらえるように事例検討をして看護を振り返る会をしてやりがいにつなげた ・LINEワークス導入でコミュニケーションが円滑となり、業務短縮につながったため、残業時間が減った。 ・管理職による年3回の職員面接を実施し精神的支援を実施している ・面談を多く ・年休取得の充実。希望休は全てとおす。勉強会の充実。不満による離職は無くなった。 |
| 取り組みの失敗例 (自由記述) |
|
・表面上はボーナスを上げたかたちになっているが、年間数万円くらいのカラクリ(会計年度職員) ・師長や副師長の退職を止められず、そんな看護部や病院なんてという雰囲気から子育てが終わった人たちがどんどん辞めることになった ・YouTubeなどで、病院の魅力を発信するとしているが、そもそも魅力がない! ・4月入職後すぐの管理職面談がないため、馴染めなくメンタル不調となった人もいた ・働き方、特に育児休暇明けの人に対して柔軟な対応を行っているが、不公平感を生んでいる ・計画的に行ったつもりの異動で、退職になってしまったこと。異動先が本人には合わなかったようです ・病院の経営問題で、雇用が厳しくなっている。離職者の再雇用が難しい |
取り組みが成果につながった例としては、業務連絡の効率化ツールを導入したことで、情報共有がスムーズになり、業務時間の短縮や残業の削減につながったとの報告もありました。
一方で、
- 計画的な異動が退職のきっかけになってしまった
- 育休明けの対応がかえって不公平感を生んだ
といった、意図しない副作用に悩む声も寄せられています。
■編集室より:「しくみ」はすぐに変えられなくても、「関わり方」は変えられる
今回のアンケートから伝わってきたのは、「辞めたくなる理由」そのものよりも、「それでも残りたかった理由」なのかもしれません。
「人間関係がきつい」「体力が限界」そんな本音があふれる一方で、「面談を増やした」「話を聴いた」「必要な人だと伝えた」といった管理者の丁寧な関わりによって、辞めずにとどまる選択ができたという声も数多く寄せられました。
病院経営が厳しく、給与や制度をすぐに変えられないなかで、管理者は、「関わり方」を変えることで離職を防ごうとしています。
たとえば──
- 就職後、1週目、3週目、3ヵ月目と面談を重ねて、課題の早期発見と対処につなげている
- 漠然とした退職希望にも、まずは「話を聴く」ことで信頼関係の土台を築いている
- 管理職による定期面談や中途採用者研修の場を増やし、チームとのつながりを意識的に支援している など
こうした取り組みは、決して「魔法のような成功例」ではありません。
けれど、関わり方を少しだけ変えることで、「ここにいてもいいかもしれない」と思える空気をつくることができる。
それは、制度や待遇よりもずっと静かで力強い離職防止のかたちかもしれません。
辞める理由をなくすことは難しくても、「続けたいと思える関係性」を育むことは、明日からでもできるのではないか。
その可能性を、今回の声が教えてくれました。
次回も、現場の声から生まれるヒントを届けていきます。
■次回アンケート予告
次回は「勤務の柔軟化とタスクシフト/シェア」をテーマに、アンケートを実施します(8月中旬予定)。お楽しみに!
「離職を防ぐ・やりがいを生み出す看護補助者の採用・定着・支援の取り組み」(ナーシングビジネス2025年7月号第2特集)
………………………………………………………