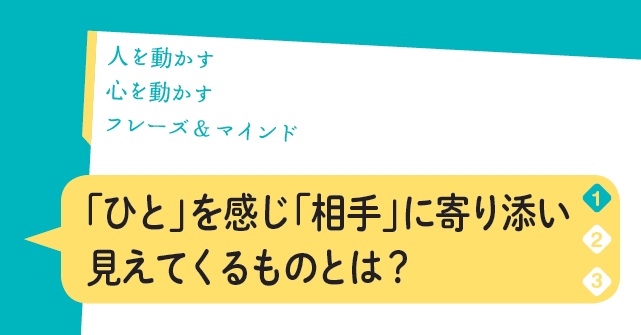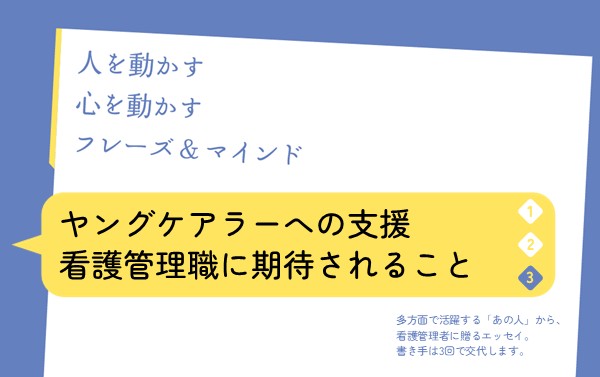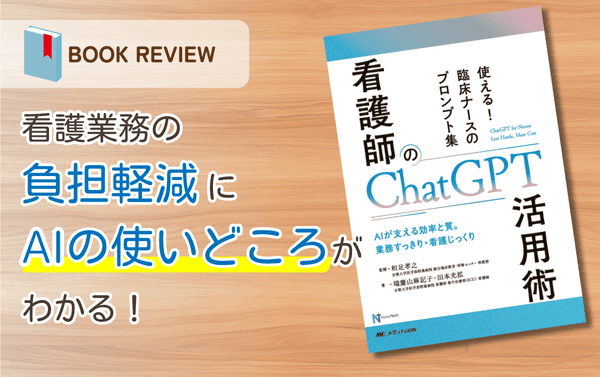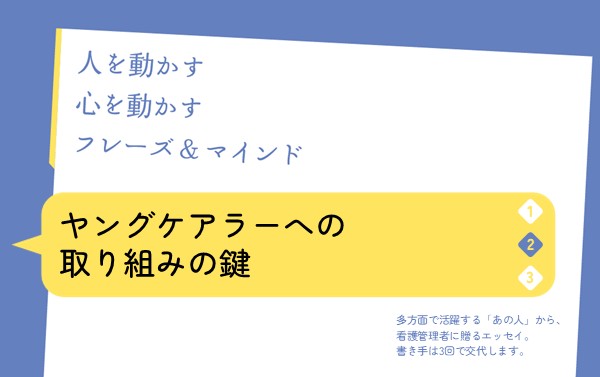私は、平城宮・京の発掘調査や、出土木簡の整理・研究等に従事している。いわば歴史研究の現場、最前線に陣取っている。その現場感覚から、少しお話したいと思う。同業者のインディアナ・ジョーンズは、映画で「考古学が求めるのはfact だ。truth ではない」と熱弁していた。仰せごもっとも。
歴史学は、証拠(史料)をもとに客観的事実を確定し、過去の人間社会を復原する。個人的感慨が入り込む余地はない。あるのは冷徹な「科学」としての歴史学の方法だ。そのせいか過去の人間社会を相手にしているわりに、歴史学、とくに古代史は、どうも「人間不在」のきらいがある。
だが、「木簡」を見ると、ぐっと「ひと」が迫ってくる。
墨書のある木片を木簡と呼ぶ。日本全国の遺跡からの出土総点数は40 万点を超える。歴史の証人とも言われ、国宝に指定されているものもある。一方、木片に書ける文字数は少ないし、小さな破片も多い。木簡から読み取れる情報は断片的だ。しかも、山の中からカツオを送ってきたりするという不可解な記述もある。だから通常の文献研究の手法ではなかなか扱いづらい。学者は木簡をしたり顔で現代的視点から解釈しようとしがちだ。現代的視点からの科学的分析だ。だが、木簡は古代の人々が作って、使って、棄てたものだ。木簡の向こうには古代人たちがうごめいている。木簡を挟んで、現代人と古代人が向き合っている、と言ってもよい。ならば古代人の側からは、それはどう見えているのだろうか。
そもそも古代人には、古代人の都合、というものがあるのだ。一見不可解な木簡の記述も、古代の「ひと」を感じて、寄り添って考えると、ふわっと見えてくる。無論、ふわっとした見通しを歴史学的方法で「fact」に鍛え上げる必要がある。かくして、山の中からカツオを送ったとする木簡の背景には、法と現実を摺り合わせる古代人のテクニックが存在していたと判明する。
科学には客観性と冷徹さが必須だ。だが同時に「ひと」を感じ 、「相手」に寄り添う感性も必要なのではないだろうか。その感性は、情緒的なものにとどまるものではなく、科学的客観性や冷徹さと結びつきながら、新たな「fact」の発見につながるものだ、と思う。

馬場 基(ばば・はじめ)
独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所 都城発掘調査部史料研究室長。研究分野は史学、日本史、史学一般。古代史・出土文字資料をはじめ日本史全体、東アジア史など幅広く研究している。
▼出典元 Nursing BUSINESS(ナーシングビジネス)2020年7月号 https://store.medica.co.jp/item/130212001
▼Nursing BUSINESS(ナーシングビジネス)トップページ https://store.medica.co.jp/journal/21.html