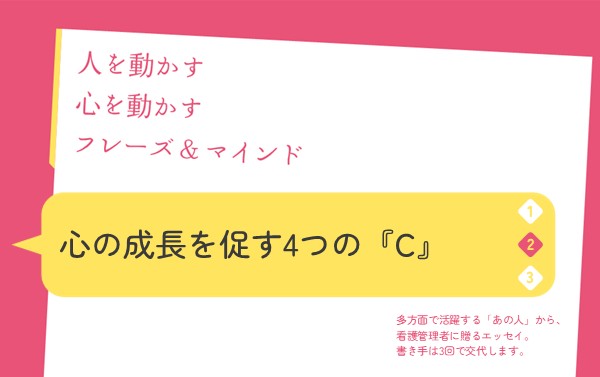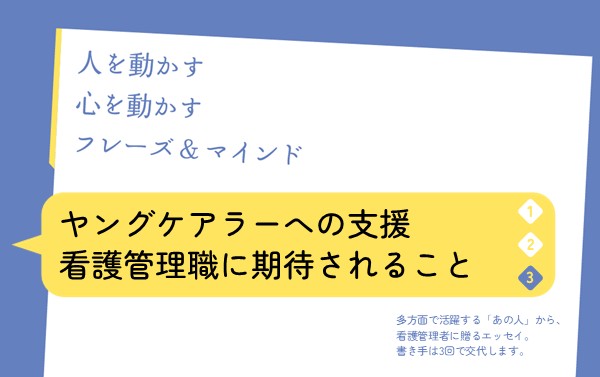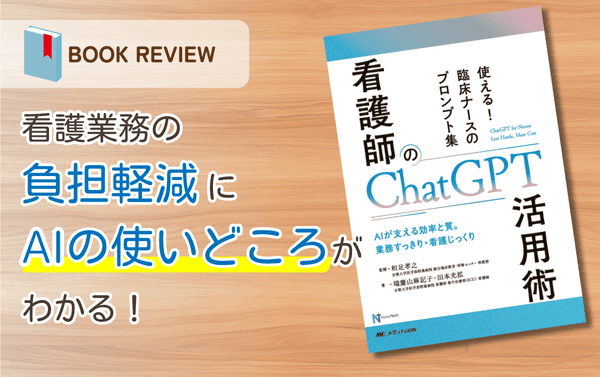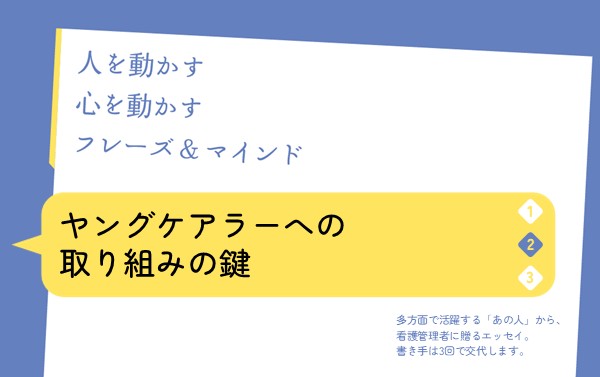スポーツカウンセラーとして長年アスリートへの心理支援を行っていると、実にさまざまな相談が持ち込まれます。
スポーツの世界は医療・看護の現場と同様に時間が切迫し、早期の決断が迫られる場面も多いです。
スポーツカウンセリングではそんなとき、何もしないことに全力を尽くす“DNA(Do Nothing Approach)”が重要だと前回お話ししました。
悩みを抱える人のそばに居続け、ともに解決策を探りながら、それでいて余分なことは何もしない。
その背景には「人生で直面する悩みや葛藤すべてが成長の糧になるはずだ」という考えがあり、私たちは困っている人を前に、本人の「自分らしく生きよう」という成長の可能性を徹底的に信じられるかどうかが問われます。
スポーツではこれをプレーヤーズ・センタード、すなわちプレーヤーの主体性を何より大切にして、彼らを中心とした競技環境をつくろうという考え方として広まりつつあります。
この考え方では、悩みや不安は自身を揺るがす「危機(Crisis)」であるが、見方を変えれば、つらいけれどもこれまでのあり方を「変化(Change)」させる絶好の「機会(Chance)」であり、それにどう「挑戦(Challenge)」するかが問われているととらえます。
筆者はこの4つのCを“悩みの4C”と呼び、相談者に気の利いたアドバイスや気休めを言いたくなったときに、DNA実践の戒めとして肝に銘じています。
不思議なことに、4Cを念頭にDNAを心がけていると、当初は八方塞がりに思えた状況が大きく改善したり、思わぬ解決策が見つかったりすることも少なくありません。
多くは「偶然」の出来事や出会いなどですが、私たちの抱える悩みの多くが、「今までのやり方ではダメだ!」と、自身のあり方に変化を迫るものだとすれば、そういう覚悟を決めたときにのみ、「災い転じて福となす」ということが成り立つのかもしれません。
前回、もしオリンピック選手村で「日本にいる家族が危篤だと聞いた」と相談されたらどうするかという例をあげましたが、そのケースでは、その家族が夢枕に立ったことで今まで伝えられずにいた思いを伝えることができ、結果として最高のパフォーマンスを発揮できました。
一見「偶然」のようでも、悩みは心の成長にとって「必然」をもたらすメッセージなのかもしれません。

土屋裕睦(つちや・ひろのぶ)
大阪体育大学教授、博士。公認心理師、スポーツメンタルトレーニング上級指導士として野球やサッカーなどのプロチーム等で心理サポートを行う。2021 年オリンピック東京大会では日本選手団のメンタルヘルスに関する緊急調査やSNS 上の誹謗中傷対策に協力。2024 年オリンピックパリ大会では日本選手団に帯同し現地で心のケアを担当。日本スポーツ心理学会理事長。剣道七段。
出典元 Nursing BUSINESS(ナーシングビジネス)2024月11月号