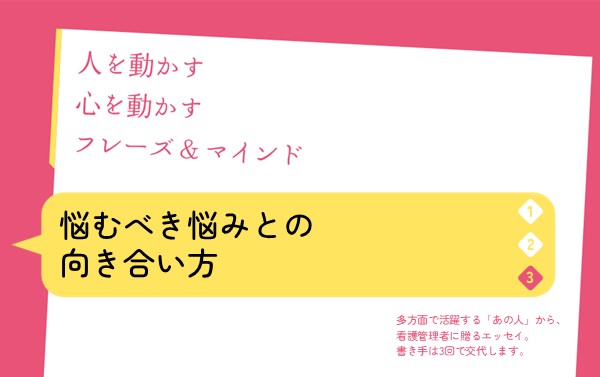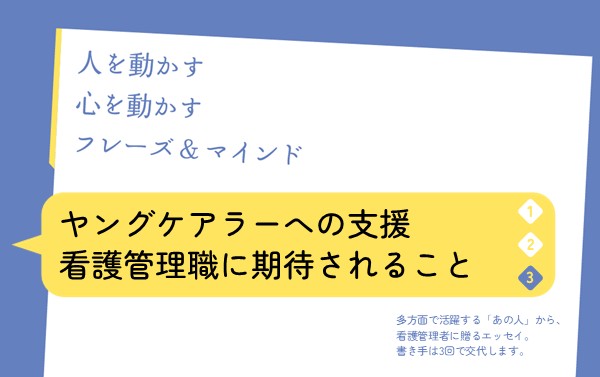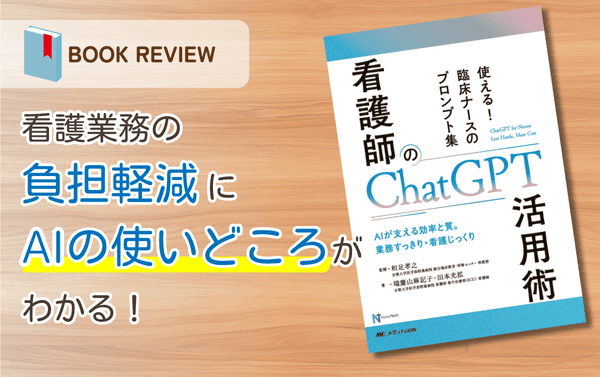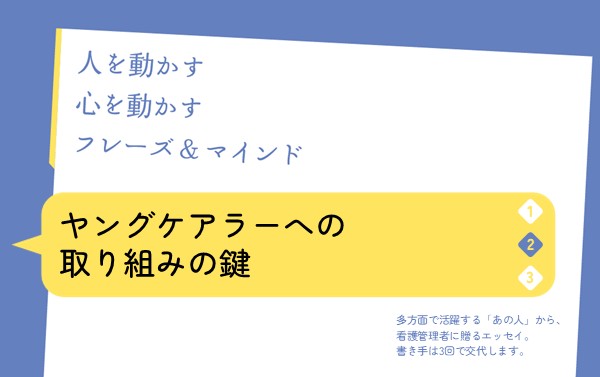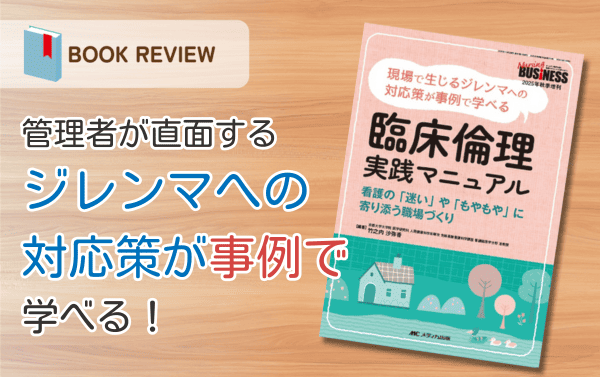看護管理者として悩みを抱える相談者を前に、どうすれば真に役立つ援助ができるでしょうか。
そのヒントとなる心理学理論に自己決定理論があります。
その前提として、私たちには①自律性(autonomy)②有能感(competence)③関係性(relatedness)という 3 つの基本的な心理欲求があると考えます。
言い換えれば、①誰かにやらされているのではなく、②自分には能力があると信じており、③ともにいる仲間とよい関係が築けていると感じたときに、主体的に問題解決に向かうというものです。
もし部下に主体性を発揮してほしいと願うのであれば、気の利いたアドバイスや、あれこれ世話を焼くことよりも、相手に決定権を与えてそれを尊重し、適切な目標を設定して達成度を評価しつつ、同時にいじめやハラスメント等のない心理的安全性が保たれた職場環境をつくることで、部下の①自律性②有能感③関係性が充足され、やる気が高まると期待できます。
何もしていないようで、主体性を発揮できる環境づくりに全力を尽くす、それがこれまでお伝えした“何もしないことに全力を尽くす DNA(Do Nothing Approach)”の具体例の一つです。
さて前回は、悩みは成長の糧になりうることに触れました。
長く相談業務に携わっていると、人生の中には「悩むべき悩み」があるように感じます。
たとえば、「自分のキャリアはこれでよかったのか」のような、漠然とした不安を感じている方がいるかもしれません。
これは「中年期危機」と呼ばれるもので、人生の半ばにあってアイデンティティの見直しを迫られているような状況です。
この悩みに主体的に取り組むことで、外的環境への適応を目指してきた人生の前半期から、自身の内面的な充実や個性化に向かう後半期への転換が図れることがあります。
悩みや不安は自身を揺るがす「危機(Crisis)」ですが、見方を変えればつらいけれどもこれまでのあり方を「変化(Change)」させる絶好の「機会(Chance)」であり、それにどう「挑戦(Challenge)」するかが問われているという「4 つの C」は、まさにこのようなことを指しています。
もし心配事や不安に直面したら、①自分の人生の主役は自分であることを忘れず ②いつか自分なりに納得できる解答の得られることを信じて ③時に気の置けない仲間と語り合いながら、悩むべき悩みに向き合っていくことが、心の成長につながると思います。

土屋裕睦(つちや・ひろのぶ)
大阪体育大学教授、博士。公認心理師、スポーツメンタルトレーニング上級指導士として野球やサッカーなどのプロチーム等で心理サポートを行う。2021 年オリンピック東京大会では日本選手団のメンタルヘルスに関する緊急調査やSNS 上の誹謗中傷対策に協力。2024 年オリンピックパリ大会では日本選手団に帯同し現地で心のケアを担当。日本スポーツ心理学会理事長。剣道七段。
出典元 Nursing BUSINESS(ナーシングビジネス)2024年12月号