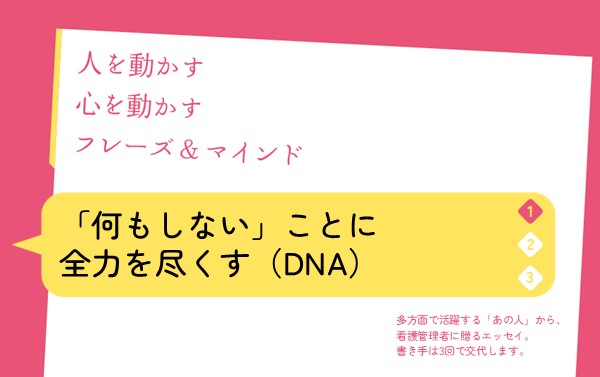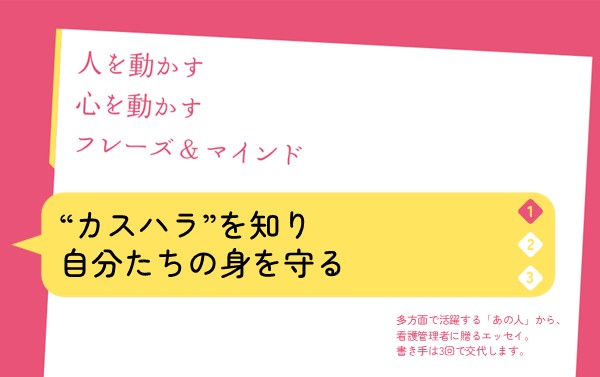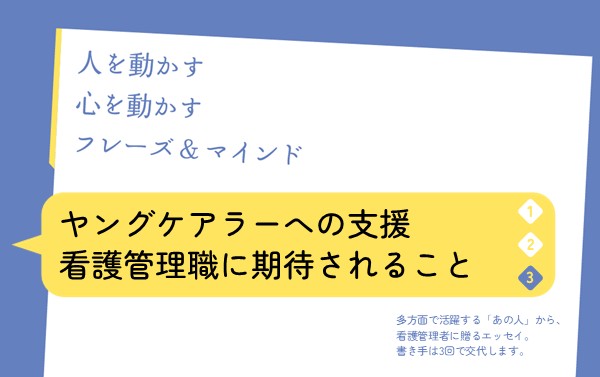オリンピック開催中のパリ、選手村からこの原稿をしたためています。
一般にアスリートは心身ともにタフで悩みなどないかのように報じられることがあります。
確かに彼らの心はしなやかですが、それを超えるようなストレスに直面することもあります。
コロナ禍で延期されて無観客で実施された東京2020大会では、アメリカの女子体操のエースが、心の不調を理由に決勝を棄権しました。
そんなこともあり、国際オリンピック委員会はアスリートの「心のケア」を重視して対策するよう各国に通知しています。
今回のパリ大会においても、敗戦につながるようなミスをした選手に対するSNS上の誹謗中傷などには見るに堪えない内容もあり、ただでさえ挫折感を味わっている選手の心が折れてしまうのではないかと心配されるときもあります。
こんなとき、アスリートやコーチをどのように支えたらよいでしょうか。
私はカウンセラーとしておよそ35年にわたって活動してきましたが、その中で大事にしていることがいくつかあります。
その一つが「何もしない」ことに全力を尽くすです。
それは冷たいのではないかと感じられるかもしれません。
しかし誰かに寄り添い、支えることがいかに難しいかを痛感してきた私は、本人の自己成長の可能性を徹底的に信じることこそが大切であり、全力を尽くし「何もしない」ことがカウンセラーのあるべき理想像ではないかと考え始めました。
私の教え子などは、この考えをDo Nothing Approach(DNA)と呼んで、次の世代にも伝えようとしてくれています。
もちろんアドバイスすることが悪いわけではありません。
育成年代ではコーチングなどを通じて教え導いてあげることも大切でしょう。
しかし、オリンピックに出場するようなアスリートやコーチの抱える悩みの答えは、本人の中からしか出てこないことが多いのです。
たとえば、いよいよ大事なオリンピックの試合の直前に近親者が危篤だと聞いたら、あなたはどうしますか?
Team Japanを離れて緊急帰国しますか?
留まって試合に臨みますか?
この答えは本人が熟考し、決断することでしか得られません。
なぜならそれは生き方の問題だからです。
カウンセラーはそこにいて、本人が悔いのない決断をするまで、何もしないことに全力を尽くして見守り続けることが求められます。

土屋裕睦(つちや・ひろのぶ)
大阪体育大学教授、博士。公認心理師、スポーツメンタルトレーニング上級指導士として野球やサッカーなどのプロチーム等で心理サポートを行う。2021年オリンピック東京大会では日本選手団のメンタルヘルスに関する緊急調査やSNS 上の誹謗中傷対策に協力。2024年オリンピックパリ大会では日本選手団に帯同し現地で心のケアを担当。日本スポーツ心理学会理事長。剣道七段。
出典元 Nursing BUSINESS(ナーシングビジネス)2024月10月号