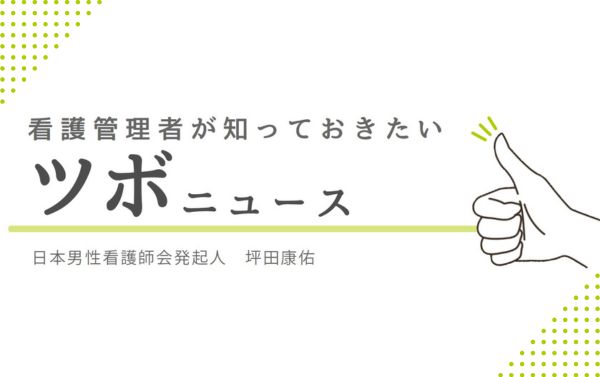看護管理者は日々多くの業務に目配り・気配りが必要です。国の施策や看護界を取り巻く状況、日々の働き方や組織づくりに関連した情報など、看護管理者が知っておきたい最新ニュースをご紹介します。
世界の看護はどこへ向かうのか
2025年の「看護の日」こと5月12日、WHO(世界保健機関)から『State of the World’s Nursing 2025(国際看護白書2025)』が発表されました。
この白書は、世界中の看護師の現状を網羅的に分析したもので、前回の2020年版から5年ぶりにアップデートされました。
今回の報告書では、看護教育、雇用、リーダーシップ、サービス提供の4つの柱に焦点を当てつつ、「教育に投資を」「看護に力を」という明確なメッセージを発信しています。
本稿では、その中からとくに日本の看護管理者にとって重要と思われる点をいくつか紹介します。
本文でも確認ができるように、〈 〉内に該当箇所を示しておきます。
5年後、看護師は足りているか?
〈Executive Summary〉
まず衝撃的だったのは、2030年における世界の看護師不足の推計が、前回の1,000万人から「1,100万人」と修正されたことです。
しかも、その7割がアフリカと東地中海地域に集中するという深刻な地域格差が強調されました。
一方で、高所得国(日本も含まれる)には世界の人口のわずか17%しか住んでいないにもかかわらず、全看護師の46%が集中しているという“過剰集積”の現状も浮き彫りにされました。
このバランスの崩れは、単なる「数」の問題ではありません。
たとえば、OECD(経済協力開発機構)諸国の中でもとくに高齢化が進む日本では、若年層看護師の確保と熟練者の継承という二重課題に直面しています。
さらに、外国人看護師の受け入れや国際的な人材の流動性も今後の看護政策の鍵を握りそうです。
日本でも2025年4月から、外国人による介護保険の訪問系サービスへの従事を認めはじめました。
看護師争奪戦は日本国内だけではなく、国際的な視点を持って実践していかなければならない時代に突入したことをあらためて考えさせられます。
学びが報われない?
―看護教育と給与のミスマッチに向き合う
〈Executive Summary のEducation〉
今回の国際看護白書2025では、世界中の看護教育のあり方と、それを取り巻く制度的な課題が詳細に分析されていました。
報告によれば、看護教育の期間として最も多いのは3年課程(53%)ですが、学士号取得への流れも着実に進んでいます。
しかし、学士課程を修了しても実際の職場において役割や給与に明確な差がないという現実が、進学意欲の低下や看護師の国外流出(いわゆる「ブレインドレイン」)を招いていることが明らかになりました。
これは、日本の看護師にとっても決して無関係な話ではありません。
日本には専門看護師(CNS)や認定看護師(CN)といったキャリアパスがありますが、再学習や資格取得にかけた労力に見合った報酬や裁量が与えられているかというと、疑問が残る場面は少なくありません。
社会保障費に限界がある日本では、これまで「予算の制約」が理由として語られることが多かったのですが、今回の白書を読むと、こうした状況は世界的な傾向であり、「学び」と「報酬」が連動していないという構造的な問題が背景にあることが見えてきます。
実際、筆者が『看護教育2025年2月号』(医学書院)に寄稿した中でも、看護師資格取得にかかる学費と年収との比較を通じて、戦後と比べて看護教育への投資対効果が著しく悪化していることを示しました。
看護職においては、教育の質や期間が長くなったとしても、それが直接的な給与向上に結びつかない現実があります。
このような状況を打破するには、医療機関が診療報酬に依存するだけでなく、新たな価値を創出していくことが必要かもしれません。
たとえば研究フィールドの提供、新商品の開発、メディアを通じた情報発信など、医療以外の収益源を確保する取り組みは、米国やインド、中国などではすでに進みつつあります。
こうした動きは、看護師の努力に報いる新たな道筋を示すものです。
日本国内でもその兆しは見られます。
たとえば慶應義塾大学医学部は、医学部発スタートアップを100社上場させることを目標とし、すでに4社が上場を果たしています。
また、個人看護師レベルでは、腎臓病の生活指導をテーマにYouTube チャンネルを運営する「看護師ざきさん」が19万人以上の登録者を持ち、医療知識をメディア収益へとつなげる成功事例を築いています。
もしかすると、これからの病院や看護部門にはこうした発想の転換、「医療だけで収益を得る」から「看護の専門性を社会価値に変える」仕組みづくりが求められているのかもしれません。
メンタルヘルスへの配慮は「盲点」
〈Executive Summary のService Delivery〉
意外だったのは、看護職のメンタルヘルス支援について、世界的に見ても制度整備が進んでいないという点でした。
調査国のうち、国・地域レベルで「看護師のメンタルケア体制」が整っていると回答したのは、たったの42%でした。
「看護職の離職率」を語るとき、待遇や業務量が注目されがちですが、コロナ禍を経てなお置き去りにされている“心のケア”の必要性が、再認識されるべき時に来ているのではないでしょうか。
日本では2015年から「ストレスチェック制度」が義務化されており、労働基準監督署へ未報告の場合は罰金が科されます。
しかし、現実にはそのデータが看護師の配置や働き方の改善に十分活用されていないのが現状です。
せっかく取得したデータが、現場の声と結びつかず、制度が“形骸化”してしまっているのです。
とはいえ、これは逆にチャンスでもあります。
世界の多くの国が同じ課題を抱えているからこそ、日本が先んじて実効性ある仕組みを整えれば、それは輸出可能な「知的財産」となり得ます。
(ストレスチェック)×(ナースの実態把握)×(改善)のPDCA―。
そんなモデルが世界標準になる日も、そう遠くないかもしれません。
リーダーがいない? それが問題
〈Executive Summary のLeadership〉
今回の国際看護白書2025で、筆者が注目したもう一つの指摘は、「政府レベルで看護職を代表するポジション(GCNO:Government Chief Nursing Officer)が存在する国は82%にのぼるが、その多くが実質的な影響力を持っていない」という点でした。
つまり、ポストはあるものの、その声が政策に反映されない―。
この構造的な問題は、何も発展途上国に限った話ではありません。
看護の声が国の政策決定過程に届きにくい構図は、実は世界共通の課題だと白書は教えてくれます。
日本に目を向けても同様です。
看護系の提言は、厚生労働省や文部科学省にどれだけ届いているのか。
現場の実情が制度や法律にどう反映されているのか。
私たちは今一度、「声の届く仕組み」があるかどうかを問い直す必要があると感じました。
たとえば、地域医療介護総合確保基金のように、国レベルで予算が組まれていても、実際の使い道は都道府県の裁量に任されます。
そこに看護職出身の議員がいなければ、現場のニーズに即した配分はなされにくいという現実もあります。
さらに、変化が激しく予測困難な“VUCA 時代”においては、「管理」ではなく「経営」の視点が求められているとも強く感じます。
たとえば、DX(デジタルトランスフォーメーション)のように、管理そのものを見直し、業務そのものを再構築するアプローチのほうが、効果的な場合もあります。
今後、看護管理者には、「看護管理」ではなく「看護経営」の視点が必要になっていくでしょう。
ところが、現在の日本の看護リーダー教育は、あくまで「看護管理」の延長にとどまっているのが実情です。
この点にも、白書の指摘を通じて「変革」の必要性を痛感させられました。
あなたの「現場」が世界につながっている
この国際看護白書の最大の意義は、「看護は国境を越えてつながっている」ということを再確認できる点にあると筆者は思います。
私たちの病院での人材不足、看護教育の悩み、リーダーシップの課題など……。
それは同時に、世界の看護職が抱えている共通の課題でもあるのです。
国や地域を超えて情報を共有し、行動を起こしていく。
その第一歩として、ぜひこの白書を一読してみてください。
一緒に看護の未来を考えていきましょう。
*****
引用・参考文献
1) WHO『State of the world’s nursing report 2025』.
https://www.who.int/publications/i/item/9789240110236(2025 年7 月15 日閲覧).
2) 看護師ざき.https://www.youtube.com/channel/UCAbl86oHLjWauHGqnRSf67Q(2025年7月15日閲覧).

坪田康佑(つぼた・こうすけ)
慶應義塾大学看護医療学部卒。Canisius College(米国ニューヨーク州)卒/MBA取得。無医地区に診療所や訪問看護ステーションを開業し、2019年全事業売却。国家資格として看護師・保健師・国会議員政策担当秘書など、民間資格ではメディカルコーチ・M&Aアドバイザーなどを持つ。
現在は国際医療福祉大学博士課程在籍、看護師図鑑(https://cango.blog/)を運営。
▼出典元:Nursing BUSINESS 2025年9月号