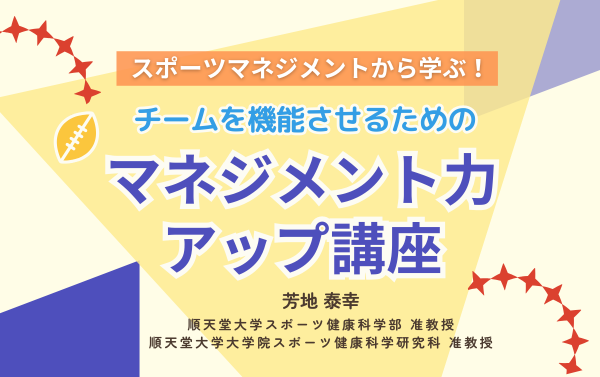第12回 BSCにおける心理的安全性の重要性(成果を上げるBSC活用術)
最終回となる今回は、昨今、注目されている心理的安全性を踏まえたBSCについて紹介します。
人間関係が悪化しない「安全な組織」とは
最近、医療機関、特に看護の分野で組織活性化を行う上で、大切とされるキーワードが「心理的安全性」です。
心理的安全性(psychological safety)とは、ハーバード大学で組織行動学を研究するエイミー・エドモンドソン(Amy C. Edmondson)氏が最初に提唱した概念とされ、「対人関係においてリスクのある行動をしてもこのチームでは安全である(自分の発言を拒絶したり罰したりしないと確信できる、人間関係の悪化を招くことがない状態)という、チームメンバーによって共有された考え」のことをいいます。
2015年に米国Google社が「心理的安全性の高い組織はパフォーマンスが向上する」と発表してから、近年では、さまざまな業界で「心理的安全性」の概念が注目されてきました。
心理的安全性において忘れてはならない点は、「心理的安全性の低い組織は環境要因によって作られることがあるが、心理的安全性の高い組織は自然に生まれない」ということです。
つまり、リーダーを中心とした組織員の努力によって、心理的安全性の高い組織は成り立つということです。
分からないことは「分からない」と言い合える
忙しい日々の業務の中で不明点があっても、忙しそうにしている人に声を掛けることは精神的に負担となり、ためらってしまうという方は多いと思います。
また、不明点があるかどうか分からないときに確認するために声を掛けることも、同様になかなか難しいものです。
仕事の場面で誰かに声を掛けるという行為は自分のタイミングで行うのではなく、相手の動きを観察した上で相手の動きを妨げず、相手の気持ちを害することのないようにと相手のことを考えて行うことがほとんどだと思います。
しかし、特に医療という人の命を扱う場面で疑問が発生する場合、小さな疑問だと思っていたものが大きなアクシデントやインシデントに発展する可能性がゼロとはいえません。
このように、小さなすれ違いが大きな問題となることを防ぐためにも心理的安全性の高い「分からないことは分からないと言い合える組織」であることはとても大切なことです。
反対に言うと、沈黙の組織は「質問がない=理解している」という訳ではないかもしれない、という視点が重要です。
表 エドモンドソン氏が提唱する心理的安全性を測定する7つの質問
| ① もしあなたがこのチームでミスをしたら非難されることが多い(逆説) ② このチームメンバーは困難な課題も提起することができる ③ このチームのメンバーは異質なものを受け入れないことがある(逆説) ④ このチームならリスクを取っても安心である ⑤ このチームメンバーに対して助けは求めにくい(逆説) ⑥ このチームには私の成果を意図的に台無しにするような行動を取る人はいない ⑦ このチームのメンバーと仕事をする中で私のスキルと才能は尊重され役に立っている |
心理的安全性の高い組織がBSCを進化させる
BSCが上手く機能しないという多くの場合、実はBSC自体が問題ではなくBSCをその組織でどのように機能させているか、という運用面で問題があるケースがほとんどです。
機能しなくなると人以外のところに原因を探そうとしがちですが、BSCはあくまで道具なので、使っている「人」が問題となるということです。
BSCは個人でも組織でも用いることのできる経営マネジメント手法です。
そして、個人の場合のほうが、多様な価値観が集まる組織で用いるよりも運用は簡単で単純です。
つまり組織での運用は難易度が高いものなのです。
つまり、心理的安全性の高い組織であることは、BSCを正しく機能させるのに大切な視点だと考えます。
特に現代という競争の激しい時代に、タイムリーな改善を行うためには欠かせない考え方なのです。
終わりに
BSCなどの目標を管理するツールは、時代により進化するものです。
心理的安全性など、ビジネスの世界で取り入れられてきた考え方なども積極的に吸収しながら、前年の方法を踏襲するだけではなく、この機会に今までのBSCの方法を、「この組織に合っているのか」という視点であらためて見直し、運用方法を進化させてみてはいかがでしょうか?
ぜひ、みなさまの医療機関で行う管理職者研修の1つに取り入れていただけたら、著者として冥利につきます。
初出:「ナーシングビジネス2023年秋季増刊」より一部改変
第11回 組織のBSC に基づいて個人のBSC や運用方法を考える

上村 久子
株式会社メディフローラ代表取締役
看護師・保健師・心理相談員
東京医科歯科大学にて看護師・保健師免許取得後、看護師実務の傍ら慶應義塾大学大学院にて企業人事・組織論を勉強。大学院卒業後、医療系コンサルティング会社にて急性期病院を対象とした経営改善に従事。 現在は病院経営アドバイザーとして、医療機関所有データ(看護必要度データ、DPC データ等)を用いた病院経営に関するアドバイスやデータ分析研修会、診療報酬勉強会、組織活性化研修等の人材育成の研修・教育サービスを提供中。
専門は、院内データを活用した病院経営、看護マネジメント、人材育成。自らの臨床経験とデータ分析能力を活かし、大学病院からケアミックス病院まで病院規模や病院機能を問わず幅広く活動している。