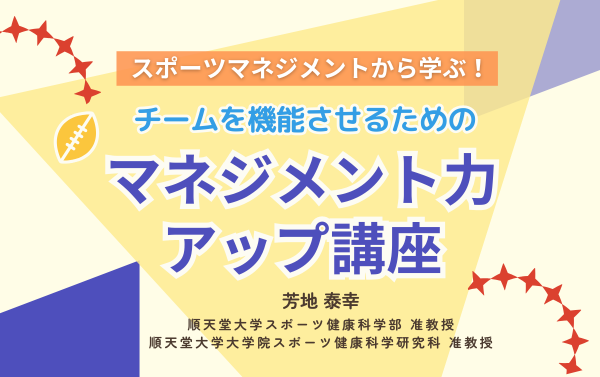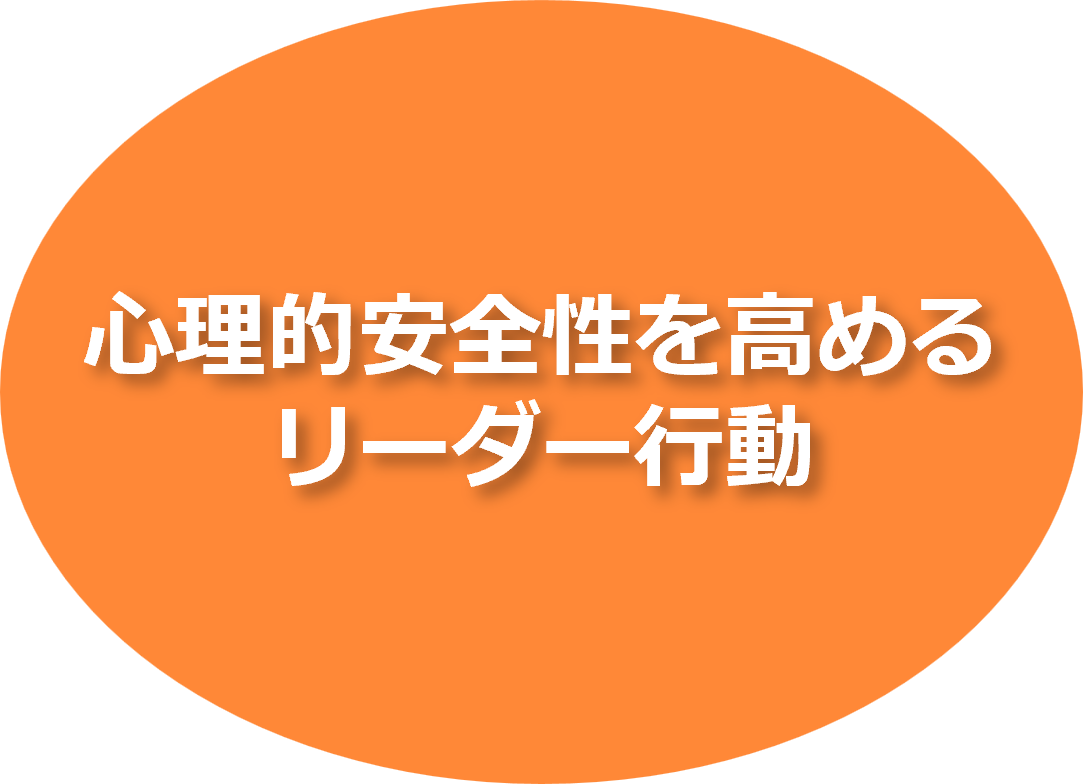スポーツマネジメントから学ぶ!
チームを機能させるためのマネジメント力アップ講座_第2回
スポーツチームと医療看護組織には共通点があります。リーダーシップやモチベーション、チーム作り、次世代の育成など、看護の明日をより輝かせるためのヒントをお届けします。
医療看護組織におけるチーミング
近年、大きな注目を集めている概念の一つに心理的安全性(psychological safety)があります。
Google社が実施した調査(プロジェクト・アリストテレス)によって生産性が高いチームは心理的安全性が高いことが報告され、その概念が世界的に注目されるようになりました。
スポーツマネジメントの分野においても例外ではなく、近年ではさまざまな分野で「心理的安全性」のみが一人歩きしているようにも見えますが、心理的安全性自体は新しい概念ではありません。
シャインとベニス(1965年)は、組織変革の文脈の中で個々人が安心して変革に取り組めるようにすることが必要であるとして心理的安全性に言及しています。
そして、エドモンドソン(2012年)は心理的安全性をチーミング (teaming)のための一つの要因として位置づけています。
医療技術の進歩による高度な医療の提供や質の高い看護・ケアに対する社会的要請は、看護師の業務をより複雑化しています。
現代では多職種連携やチーム医療の実現、働きがいのある職場づくりなど、さまざまなことが求められています。
①ミスを最小限にしながらも複数の目標を達成する、②多様な他者との協働や高いレベルのコミュニケーションと緊密な協調を維持しながら、次から次へとさまざまな状況に対応する、③複雑な情報を素早く処理・統合・活用する、といったことが日常的に期待されているのではないでしょうか。
そのようななか、リーダーとしてメンバーに学習を促し、チームを機能させるためにはどうすればよいのでしょうか。
チーミングとは、「新たなアイディアを生み、答えを探し、問題を解決するために人々を団結させる働き」です。
それは動的なプロセスであり、絶え間ないチームワークと学習を促すものです。
チーミングにおいて、心理的安全性の確保は欠かすことができない重要な要因となります。
エドモンドソン(2012年)は心理的安全性を高めるためのリーダーの具体的な行動として、以下の8点を挙げています。
|
❶ 直接話のできる、親しみやすい人になる ❷ 現在持っている知識の限界を認める ❸ 自分もよく間違うことを積極的に示す ❹ 意見を求め、参加を促す ❺ 失敗は学習する機会であることを強調する ❻ 客観的かつ率直な表現、具体的な言葉を使う ❼ 非難に値する行為、望ましい行為の境界を明確にする ❽ 境界を越えた際、適切かつ一貫した方法で責任を負わせる |
職場づくりと心理的安全性
心理安全性の高い職場をつくるうえで、心理的に安全な職場がどのような状態を指すのかについてメンバー間で共有された見解をつくっておくことも大切です。
チームの心理的安全性とは「チームは対人関係においてリスクを取っても安全であると共有された信念」と定義されます。
それは、単に寛容的でも好意的であるというわけでもなく、発言した誰かを困惑させたり、拒絶したり、罰したりすることはないという確信がある状態を意味しています。
つまり、心理的安全性が確保されている状態とは、スタッフがおのずと仲良くなるような居心地のよい状況を意味するものではありません。
プレッシャーや問題がないことを示唆するものでもありません。
むしろ、心理的安全性によってもたらされるのは、率直な会話、厳しいフィードバック、真実を避けずに話し合うことなど、一般的には抵抗感があり避けられがちな必要かつ重要なものです。
そのため、心理的安全性の高いチームにおいては、意見の対立も厭わず率直な議論が行われるのです。
反対意見を出して葛藤が生まれても、私の居場所はここにあり続けると安心できること、心理的に守られていると感じられることが重要なポイントになります。
また、手助けや情報を求めても、不快に思われたり恥をかかされたりすることもないと思えることも心理的安全が高い職場の特徴といえます。
そして、このような信念(確信)は、人々が互いに信頼し、尊敬しあっているときに生まれてきます。
これらについて、メンバー間で共通の見解をつくり、心理的安全性を正しく捉えることも実践において重要なリーダーの役割ではないでしょうか。
スポーツチームの指導者(たとえば監督)とは異なり、医療看護組織ではプレイングマネジャーという立場の方もいらっしゃるでしょう。
管理職やリーダーというと、とにかく自分自身に過大な責任や期待をかけ、背負おうとするものです。
リーダー自身が奮闘することはもちろん必要ですが、自分自身の頑張りだけでなく、メンバーたちに持てる力を最大限発揮してもらい、知恵を結集して新たな解決策を創出することでより大きな成果を生みだすことも重要な役割です。
「全体は部分の総和に勝る」という言葉があるように、メンバーの力を信じ、メンバーの力を最大限活用することで相乗効果を引き出して組織の力に変えていくこと、学習し続けるチームをつくっていくこともリーダーの重要な仕事であるといえます。
引用・参考文献
1) Edmondson, A. Teaming:How Organizations Learn, Innovate, And Compete In The Knowledge Economy.Jossey-Bass. 2012
(野津智子訳.‘‘チームが機能するとはどういうことか「学習力」と「実行力」を高める実践アプローチ”.東京,英治出版,20 I 4, 392p.)
2) Schein, EH and Bennis, WG. Personal and Organizational Change through Group Method. New York, Wiley,1965
………………………………………………………
【次回予定】第3回「部下の力を引き出すモチベーションの科学」です。お楽しみに!
芳地泰幸(ほうち・やすゆき)
順天堂大学スポーツ健康科学部准教授
順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科准教授(併任)
香川県生まれ。順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科博士後期課程単位取得満期退学後、聖カタリナ大学講師、日本女子体育大学准教授を経て現職。公益財団法人大原記念労働科学研究所協力研究員。マネジメントの視点から組織活性化や職場の創造性、リーダーシップ開発について研究している。博士(スポーツ健康科学)。
『自分を知ることから始まるリーダーの第一歩』(スポーツマネジメントから学ぶ!
チームを機能させるためのマネジメント力アップ講座_第1回)