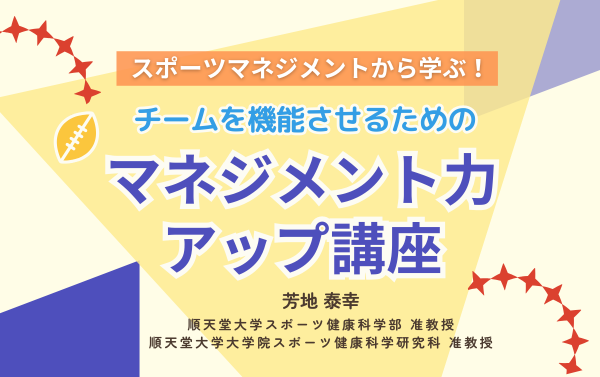スポーツマネジメントから学ぶ!
チームを機能させるためのマネジメント力アップ講座_第8回
スポーツチームと医療看護組織には共通点があります。
リーダーシップやモチベーション、チーム作り、次世代の育成など、看護の明日をより輝かせるためのヒントをお届けします。
看護管理者に求められる2つの視点
スポーツチームが成果を出すには、選手一人ひとりが自らの能力を高めるだけでなく、選手全員が持てるカを発揮し、チームとして機能することが欠かせません。
ラグビー日本代表が掲げたスローガン「One Team」は、まさにその象徴です。
ポジションや役割は異なっても、全員が共通の目的に向かって力を合わせることで、個の力を超えた成果を生み出しました。
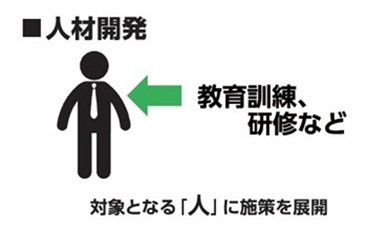
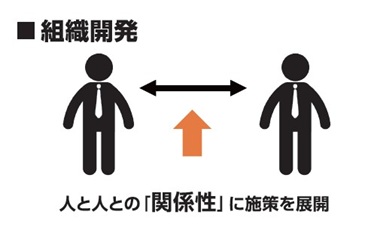
図 人材開発と組織開発の視点
スポーツと同様に、医療の現場でも、一人の優秀な看護師だけでは質の高いケアは実現できないでしょう。
そこで重要になるのは、「人材開発」と「組織開発」を両立させる視点です。
人材開発:一人ひとりの成長を支える
人材開発とは、スタッフの能力やキャリア形成など、個人に焦点を当てた取り組みです。
スポーツにおいては、選手それぞれの能力を最大限に引き出すために、ポジションや役割に応じたトレーニングやキャリア開発が行われます。
新人選手には基礎技術の習得を重視し、ベテランにはリーダーシップの発揮を期待するなど、成長段階に応じた支援が欠かせません。
医療看護組織における新人看護師の教育、OJT、研修、キャリア面談、専門認定看護師の育成などは人材開発の典型例といえるでしょう。
ここで看護管理者に求められるのは「スタッフの強みや可能性を見きわめ、それを発揮できる機会を作ること」です。
さらに近年は、キャリア志向やライフステージの多様化が進み、単に医療ケア技術の向上を求めるだけでなく、ワークライフバランスや専門性追求など、個々のニーズに応じた支援が重要になっています。
そこで特に有効なのが、「タスク学習(task learning)」と「人的学習(human learning)」の2つの観点です。
| タスク学習 | 業務を通じて知識やスキルを獲得し、能力や適応力を高める |
| 人的学習 | キャリアやアイデンティティを育み、人生全般に関わる成長を促す |
この2つを意識的に組み合わせることで、看護管理者はスタッフー人ひとりの成長を効果的に支援でき、組織全体の力を高める基盤を築くことができます。
組織開発:チーム全体の力を高める
試合で勝つためには、戦術や技術だけでなく、チームワークや信頼関係が不可欠です。
監督やコーチは、選手同士のコミュニケーションを促し、心理的安全性を確保し、共通の目標を共有することでチームをまとめあげます。
組織開発とは、チーム(病棟や部署)全体の学習力や適応力の向上など、人と人との関係性に焦点をあてた取り組みです。
風通しのよい職場づくり、対話の促進、組織文化の改善などが含まれます。
どれほど優秀な看護師を育てても、組織が整っていなければその力は発揮されません。
逆に、組織が学び続ける文化をもてば、個人の成長もいっそう加速します。
たとえば、カンファレンスや定例会議を単なる情報伝達で終わらせず、「意見交換や学びの共有の場」に変えることは、小さな組織開発の実践といえます。
組織開発の取り組みを効果的に進めるためには、次の4つのプロセスを意識することが有効です。
■ 組織開発の4つのプロセス
①目指す姿に照らし、事実をもとに現状を把握する
「職場が疲弊している」といった印象だけで判断せず、インタビューやサーベイを通じて事実に基づいた現状把握を行う
②キーパーソンを巻き込み、課題解決の必要性を合意する
影響力のあるスタッフを早期に巻き込み、課題解決の必要性を共有する
③スモールスタートで早期の成果を示す
小規模な病棟やチーム単位で試みを始め、早い段階で成果を示す
④施策を拡大し、組織が「自走」する仕組みを整える
成功要因を分析し、病院全体に広げる。現場が自律的に継続できる仕組みを整える
■ 組織開発の具体的手法
組織開発を推進する際には、対話や協働を通して組織の学習力を高めるための多様な手法が活用されます。
代表的なものを表に紹介します。
| ①コーチング | 相手を傾聴し、相手を承認することで自発的な気づきや行動を引き出す手法 |
| ②チームビルディング | 協働作業やグループワークを通じて自己理解と他者理解を促し、相互理解と信頼に基づく協働的な組織風土を築く手法 |
| ③フューチャーサーチ | 時系列を意識しながら未来のあるべき姿を描き、そこから行動計画を策定する全員参加型のワークショップ |
| ④ワールドカフェ | 小グループに分かれて対話し、柔軟にメンバーを入れ替えながら知識や意見を交換する会議手法 |
| ⑤アプリシエイティブ・インクワイアリー | 「何がうまくいっているか」「組織の強みは何か」に焦点を当て、課題解決型ではなくポジティブ・アプローチによる探求や質問を通して組織の価値を認め、高めていく手法 |
おわりに
チームを機能させるために、人材開発と組織開発は看護管理者にとって避けて通れない重要なテーマです。
スタッフにリーダー役を任せることは、その看護師の貴重な成長の機会であると同時に、チーム全体の新たな挑戦を促す組織開発の実践でもあります。
その過程で得られるフィードバックや多職種との協働経験は、人的学習を通じてさらなる成長につながるでしょう。
このように看護職一人ひとりのキャリア形成を支援しつつ、組織全体の学習力を高めることで、変化の激しい現代の医療環境においても柔軟かつ持続的な成長を成し遂げることができるのではないでしょうか。
そのなかで「個人の成長をいかに組織の成長へと結びつけるか」という問いを持ち続ける姿勢こそ、看護管理者に求められる姿ではないでしょうか。
引用・参考文献
1)加藤茂夫.ニューリーダーの組織論東京,泉文堂,2002.
2)金井壽宏ほか.[新版]組織行動の考え方:個人と組餓と社会に元気を届ける実践知.東洋経済新報社,2025.
………………………………………………………
【次回予定】第9回は「未来のリーダーを育てる看護部長の役割」です。お楽しみに!
芳地泰幸(ほうち・やすゆき)
順天堂大学スポーツ健康科学部准教授
順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科准教授(併任)
香川県生まれ。順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科博士後期課程単位取得満期退学後、聖カタリナ大学講師、日本女子体育大学准教授を経て現職。公益財団法人大原記念労働科学研究所協力研究員。マネジメントの視点から組織活性化や職場の創造性、リーダーシップ開発について研究している。博士(スポーツ健康科学)。
『もめごとを乗り越える』(スポーツマネジメントから学ぶ!チームを機能させるためのマネジメント力アップ講座_第7回)