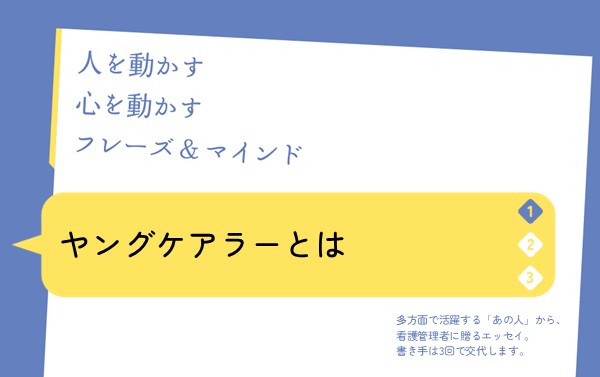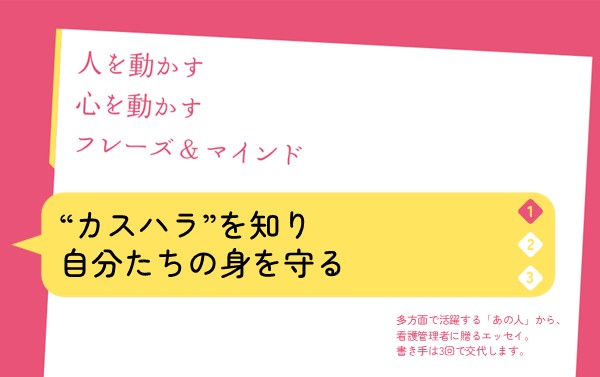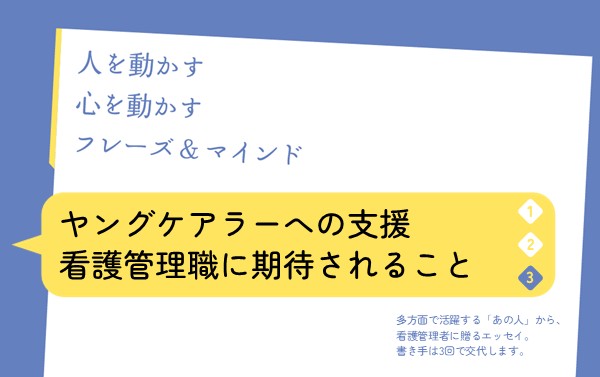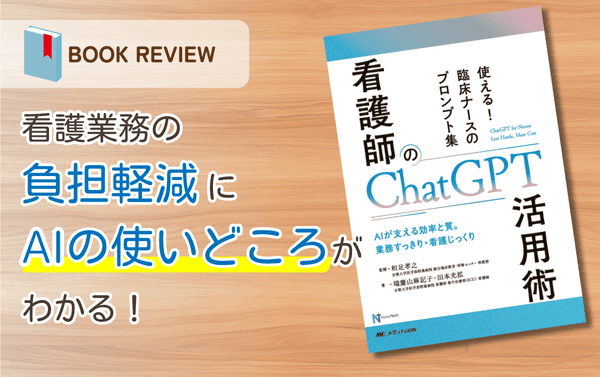筆者は、病気や障害のある家族等の世話をするヤングケアラーと呼ばれる子ども・若者の支援・研究に取り組んでいます。
ヤングケアラーについて、子ども・若者育成支援推進法は、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義しています。
ヤングケアラーは、身体障害や知的障害、精神障害、慢性疾患、高齢等により、介護や世話、見守りを必要とする状態にある大人の世話をしています。
その対象の多くは親やきょうだいですが、祖父母や他の親族の場合もあります。
現在、日本においてヤングケアラーは少なくない規模でいることがわかっています。
たとえば、2020年および2021年に厚生労働省と文部科学省とが全国の小中高生および大学生を対象に実施した調査は、「世話をしている家族がいるか」との問いに、「いる」と答えた人の割合は、小学6年生で6.5%、中学2年生で5.7%、全日制高校2年生で4.1%、大学3年生で6.2%であると報告しています。
この結果から、子ども・若者の16人から25人に1人がヤングケアラーであると推測されます。
つまり、多くの子ども・若者が、成人のケアラーとともに、世話を必要とする人の尊厳ある生活を支えているのです。
ヤングケアラーは、世話をすることによりさまざまな影響を受けています。
世話をすることによって、人間的に成熟する、自律的になる、利他的で共感的になるなど、よい影響を受ける一方で、適切な支援がない場合には、世話をすることによって、ストレスや疲労が蓄積する、学校に遅刻したり欠席したりする、友人と遊ぶ時間を持てないなどの、よくない影響を受けます。
このように、世話をすることにより自身の健康や教育、社会関係等によくない影響を受けることから、ヤングケアラーは支援の必要な子どもであると考えられます。
ヤングケアラーについて、2024年6月に改正された子ども・若者育成支援推進法は、国・自治体が各種支援に努めるべき対象に定めています。
ヤングケアラーが他の子ども・若者と等しくライフチャンスを得られるようにするための取り組みが、それぞれの自治体で進むことが期待されます。

森田久美子(もりた・くみこ)
立正大学社会福祉学部社会福祉学科 教授。研究分野は精神保健ソーシャルワーク、ケアラー支援。一般社団法人日本ケアラー連盟理事として、ヤングケアラーを支援するための政策提言等に取り組む。
出典元 Nursing BUSINESS(ナーシングビジネス)2025月4月号