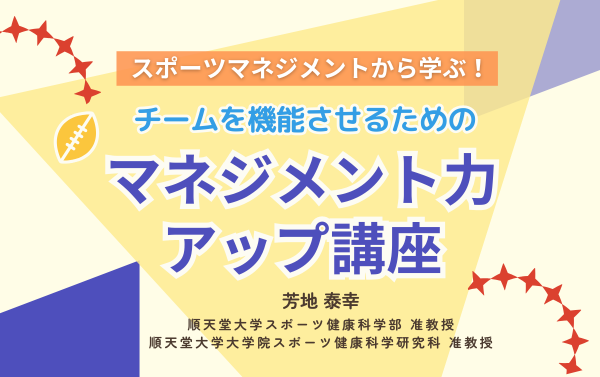スポーツマネジメントから学ぶ!
チームを機能させるためのマネジメント力アップ講座_第5回
スポーツチームと医療看護組織には共通点があります。
リーダーシップやモチベーション、チーム作り、次世代の育成など、看護の明日をより輝かせるためのヒントをお届けします。
コミュニケーションの重要性
スポーツチームでは選手同士の水平的な意思疎通だけでなく、監督やコーチとの垂直的なコミュニケーションも不可欠です。
特に重要な試合の場面では、戦術や戦略を選択・実行に移す際、選手同士の意思疎通に加えて、監督・コーチとの信頼関係を基盤としたコミュニケーションが勝敗を左右します。
コミュニケーションとは、言葉で交わされる言語的なやり取りだけではありません。
表情や態度などの非言語的な要素、さらにはメッセージの裏にある心理的なやり取りも含まれます。
チームがうまく機能しない原因や、人間関係上のコンフリクト(対立や葛藤)の多くは、コミュニケーションの不十分さに起因しています。
したがって、効果的なチームワークの実現には、豊かなコミュニケーションが欠かせません。
読者の皆さんが職場で費やしている時間の多くは、「読む、書く、話す、聴く」といったコミュニケーション活動にあてられているのではないでしょうか。
つまり、メンバー間での意思疎通や情報共有、協カ・調整といったコミュニケーションがなければ組織は成り立たないのです。
組織論で知られるステファン・ロビンス(Stephen Robbins)は、コミュニケーションの主な機能として、①統制(コントロール)、②動機づけ(モチベーション)、③感情表現、④情報の4つをあげています。
管理職者がスタッフ(部下)に指示を出す、情報を共有する、職務へのモチベーションを高める、さらには職務への満足や不満足といった感情を周囲に表現することによって社会的欲求を充足することもコミュニケーションの重要な機能になります。
チームワークを育むための「ストローク」
1950年代に、精神科医であるエリック・バーン(Eric Berne)によって提唱された交流分析(Transactional Analysis)は、チームワークの向上や選手同士や指導者(監督・コーチ)との良好な人間関係を構築するためのコミュニケーション・トレーニングに活用されるなど、近年のスポーツマネジメントの分野でも注目されています。
その中心概念のひとつに「ストローク(stroke)」があります。
ストロークとは、日本語に直訳するのが難しい英単語ですが、「人に働きかける」という意味で捉えられています。
チームメイトに声をかけたり、挨拶したりするといった何気ない行為もすべてストロークといえます。
換言すると、その人の存在を認めることを交流分析ではストロークと呼びます。
人は誰でも無視されたくない、自分の存在を認めて欲しいという基本的欲求を有しているというのが交流分析の大前提であり、ストロークはすべての人間関係の基本であると位置づけられています。
ストロークには様々な種類があり、以下の観点から分類されます(表1)。
まず、ストロークには肯定的なものと否定的なものがあります。
たとえば、温かい肌の触れ合い、心温まる言葉、親しみのこもったジェスチャーなどは、ポジティブなストロークです。
それに対して、殴る、叱る、睨むなどはネガティブなストロークといえます。
次に、ストロークは身体的ストロークと精神的ストロークに分けることができます。
身体的ストロークはタッチ・ストロークとも呼ばれます。
身体的な接触をしない他者への目配せなどの非言語的な働きかけもストロークであるので、精神的ストロークは言語的と非言語的とに分けることもできます。
さらに、ストロークには、その人が存在していることそれ自体に与えられる「無条件」のストロークと、その人の行動や行為あるいは属性などに与えられる「条件付き」のものがあります。

これを前述のポジティブ・ストロークとネガティブ・ストロークと組み合わせると、次のような4つの分類ができます。
(a)無条件のポジティブ・ストローク:「一緒にいるだけで安心する」、 (b)条件付きのポジティブ・ストローク:「練習に打ち込む君が好き」、(c)条件付きのネガティブ・ストローク:「その対応は適切ではなかったね」、(d)無条件のネガティブ・ストローク:「キミに用はない!」というようになります。
適切なストロークの交換がチームを強くする
あなたは日頃、どのようなストロークを周囲に送ることが多いでしょうか?
どのようなストロークを受けとることが多いでしょうか?
対人関係においてはポジティブ・ストロークの交換が理想的です。
しかし、どうしてもネガティブなストロークを送らなければならないこともあるでしょう。
そのときは条件付きで送ることが重要です。
たとえば、「申し送りではきちんと発言して正確に情報を伝えてください」というように、その人の存在に対してではなく、「行動」に対して指摘するという視点が大切です。
また、「今日のカンファレンスはどうしたの?」というように、時点や場面を区切って伝えることで、相手の軌道修正を支援することも可能になります。
効果的なチームワークを育むためには、日常的な対人間コミュニケーションにおいて、適切なストロークの交換が重要になります。
適切なストロークの交換がコミュニケーションを豊かにし、チームの力を最大化する鍵となるのです。
引用・参考文献
1)Stephen P. Robbins. Essentials ofOrganizational Behavior 8th ed., Prentice Hall, 2025.
(高木晴夫訳.新版組織行動のマネジメント.東京,ダイヤモンド社,2009).
2) 北森義明.組織が活きるチームビルディング一成果が上がる,業紙が上がる.東京,東洋経済新報社,2008.
3)水野碁樹編著.リーダーシップ理論の新機軸ースポーツマネジメントと組織論のダイナミズムー.東京,創成社,2025.
………………………………………………………
【次回予定】第6回は9月配信で、「部下の成長を支えるキャリア開発の視点」です。お楽しみに!
芳地泰幸(ほうち・やすゆき)
順天堂大学スポーツ健康科学部准教授
順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科准教授(併任)
香川県生まれ。順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科博士後期課程単位取得満期退学後、聖カタリナ大学講師、日本女子体育大学准教授を経て現職。公益財団法人大原記念労働科学研究所協力研究員。マネジメントの視点から組織活性化や職場の創造性、リーダーシップ開発について研究している。博士(スポーツ健康科学)。
『チームカを最大化する方法』(スポーツマネジメントから学ぶ!チームを機能させるためのマネジメント力アップ講座_第4回)