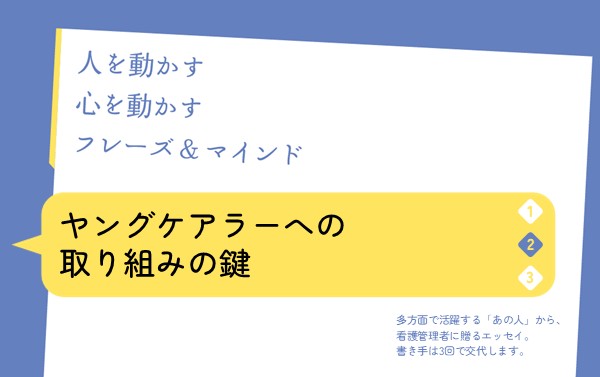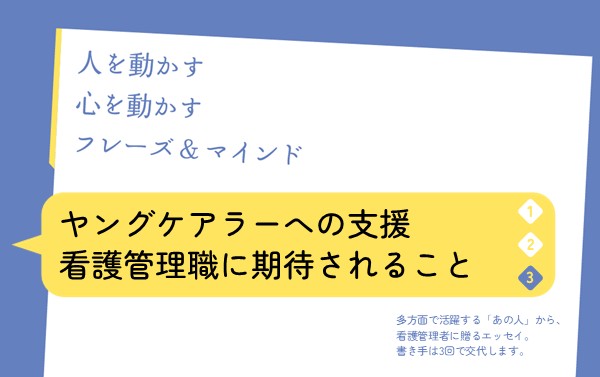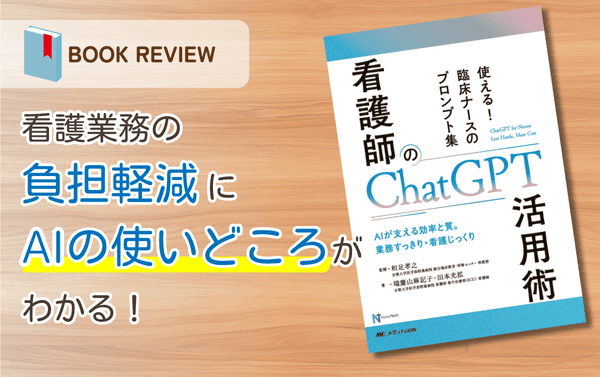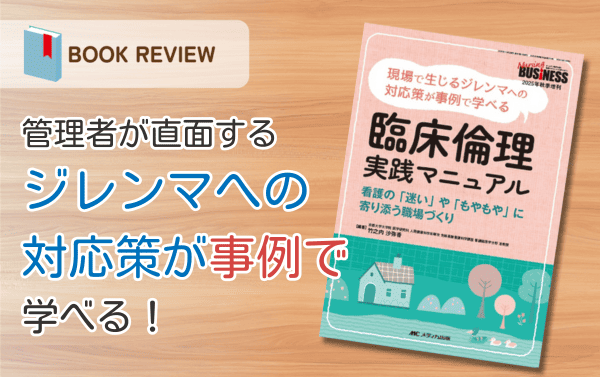ヤングケアラーとは支援の必要な子ども・若者であることを、前回お話しました。
ヤングケアラーは、家族の世話をすることによりさまざまな影響を受けることから、各自治体における支援等の促進が期待されています。
ヤングケアラーへの取り組みにあたり鍵となるのは、ヤングケアラーを発見することです。
なぜなら、ヤングケアラーは表面化しにくいため、子ども・若者を支援する公的支援機関から見えず、必要な支援が届きにくいという支援上の課題があるからです。
ヤングケアラーは、「家族の世話は家族で」という価値観や、家族が非難されることへの懸念等から、自身が家族の世話をしていることを家族外の人に話さない傾向にあります。
また、公的支援機関を含む家族外の人々は、家庭内の様子が見えず、子ども・若者が支援の必要な状態にあることに気づかないことがあります。
加えて、子ども・若者の周りにいる人々がヤングケアラーについて知らないことで、ヤングケアラーが見過ごされてしまうこともあります。
このようにヤングケアラーは表面化しにくく、必要な支援を受けづらい構造にあることから、ヤングケアラーへの取り組みにおいては、ヤングケアラーを見つけ、支援することのできる体制を各自治体において発展させることが重要です。
では、ヤングケアラーを発見できるのは誰でしょうか。
ヤングケアラーを発見できる人には、子ども・若者が通う学校の教職員や、世話を必要とする人が利用する医療機関や福祉機関の職員が挙げられます。
中でも、医師や看護師などの医療機関の職員はヤングケアラーを発見できる重要なポジションにいます。
というのも、医療機関の職員は、病気や障害により世話を必要とする人を看ており、その人の家族状況を把握する中でヤングケアラーに気づくことができるからです。
また、医療機関の職員は、子ども・若者やその家族にとって家族の病気や障害のことを隠す必要がなく、気兼ねなく話すことができる存在でもあります。
このように医療機関の職員は、ヤングケアラーの視点を持って日々の診療活動に取り組むことで、ヤングケアラーを発見できる重要なポジションにいるといえます。

森田久美子(もりた・くみこ)
立正大学社会福祉学部社会福祉学科 教授。研究分野は精神保健ソーシャルワーク、ケアラー支援。一般社団法人日本ケアラー連盟理事として、ヤングケアラーを支援するための政策提言等に取り組む。
出典元 Nursing BUSINESS(ナーシングビジネス)2025月5月号