第2回 目標を組織で楽しむための3つのポイント(成果を上げるBSC活用術)
目標設定は「望んでいること」かつ「現実的であること」
目標設定は、その人やその組織が本当に望んでいることが大前提です。
「本当はどうなりたいか?」を考えますが、それはただの願望ではなく、現実的に達成可能かどうかという視点がなければ、達成はおろか心理的にも不安定な状態に陥ってしまうことは容易に想像できてしまいます。
同じ目標が繰り返されている場合には、その状態が当たり前になってしまい「また目標が達成できないかもしれない」「目標が達成できなくても仕方がない」と無意識に思い込んでしまうものです。
もし達成できれば理想的な組織になるという目標であったとしても、その目標が絵に描いた餅になってしまっていては、心から楽しんで取り組むことはできません。
まずは楽しめる目標にするために、「本当に望んでいること」は大前提として、そうなっている自分たちが想像できるかどうか、すなわち「現実的に達成可能であるか」が重要なのです。
達成過程を「楽しめ」かつ「当事者意識を持てること」
目標を設定したら、あとは改善を実行し、達成するのみ。
目標を設定した時点で楽しめるかどうかが決まるといっても過言ではありませんが、その先の道のりを楽しめた方がよりよいことは言うまでもありません。
達成した方がよい目標を掲げたわけですから、当然、目標達成に向けた日々の工夫が必要になります。
例えば目標を意識し続ける工夫として、病棟に目標を掲げている組織も目にしますし、朝礼で唱和している組織もあると思います。
意識し続けるという目的が達成できていればよいのですが、それが日常の業務に生かされていないのであれば、もう一工夫する必要があると思います。
声に出したり目に見えるところに置くだけではなく、例えばカンファレンス等で、「目標について意識ができているかどうか」を数分間でよいので数人で考える時間をつくるというのも簡単な工夫のひとつです(図)。
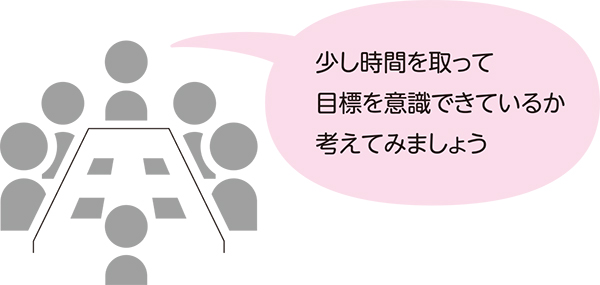
また、目標が掲げられていても、当事者意識を持てないと組織としての達成に結びつきませんし、達成できたとしても達成感という楽しみにはつながりにくいものです。
お互いに意識し合えるよう、例えば目標達成に向けた個人の努力を中間評価する時間や場所を決めることで、目標達成という意識を高め合えるだけではなく組織としての一体感を構築できるという効果もあります。
ポイントは、その組織に属する職員に合わせた工夫をすることです。
みなさまの組織にはどんな職員の方がおられますか?
若い方が多い組織ですと、改善に向けた勢いはよいのですが方向性が間違うことのないよう短いスパンで進捗確認し、軌道修正が必要になると思います。
また、変化することに対して慎重な性格の方が集まる組織ならば、変化に伴う心理的な不安に耳を傾けられるよう声を掛け、実際に現場で変化を促すことが必要になると思います。
もしお一人で自組織に合う工夫を考えることが難しければ、ぜひ組織みんなで相談されてはいかがでしょうか。
目標達成の楽しみを循環させると改善し続ける組織ができる
BSC等の経営マネジメント手法は、組織が永続的に存在し続けるために必要な仕組みです。
私が考える組織を継続させるためのポイントは、「楽しむことを循環させること」です。
経営マネジメント手法を用いている組織ならば、目標の振り返りは必ず行っていると思いますが、どのように行っているでしょうか?
例えば、所属長である病棟師長のみが文書で振り返りを行い、看護部に提出するという形を取っているところも多いと思います。
はたして、これはよいことなのでしょうか?
振り返りの目的を考えてみましょう。
振り返りとは、自分たちが努力したことを認め合い、時に慰め、自分たちの組織の力を確認し、求心力を高め合うことでです。
そして、次の目標に向けて自分たちの立ち位置を共有することです。
このような組織全体を巻き込んだ振り返りを行っていると、努力ができる組織であることを喜びあえるため、よい改善の循環が生まれます。
所属長のみの視点で振り返りを行っても、多角的な振り返りができないため、本当に評価すべきことや改善しなければならないこと等を見逃してしまうことになりかねません。
楽しむためには、改善に向けて努力をしてきた組織全体を巻き込むことが必要です。
みなさまの組織では振り返りはどのように行っていますか?
「次の目標に向けて頑張ろう!」とスタッフ全員と心をひとつにすることがどれほどできているでしょうか。
たくさんの時間を取れなくとも、5分程度のわずかな時間であっても、振り返りの時間を持つことをお勧めします。
初出:「ナーシングビジネス2023年秋季増刊」より一部改変

上村 久子
株式会社メディフローラ代表取締役
看護師・保健師・心理相談員
東京医科歯科大学にて看護師・保健師免許取得後、看護師実務の傍ら慶應義塾大学大学院にて企業人事・組織論を勉強。大学院卒業後、医療系コンサルティング会社にて急性期病院を対象とした経営改善に従事。 現在は病院経営アドバイザーとして、医療機関所有データ(看護必要度データ、DPC データ等)を用いた病院経営に関するアドバイスやデータ分析研修会、診療報酬勉強会、組織活性化研修等の人材育成の研修・教育サービスを提供中。
専門は、院内データを活用した病院経営、看護マネジメント、人材育成。自らの臨床経験とデータ分析能力を活かし、大学病院からケアミックス病院まで病院規模や病院機能を問わず幅広く活動している。






