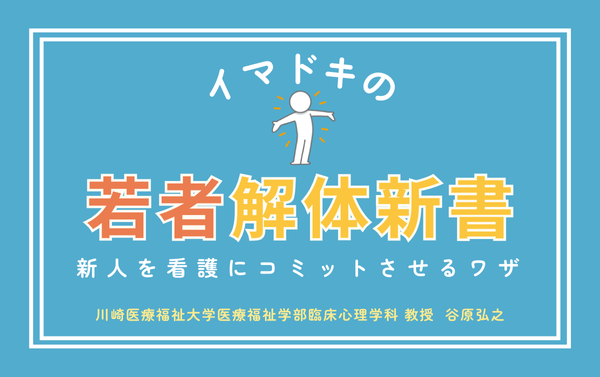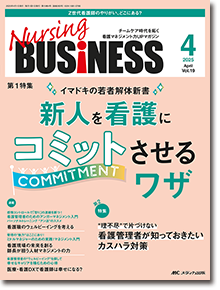イマドキの若者解体新書:
新人を看護にコミットさせるワザ_第1回
私は心理学の専門家(公認心理師・臨床心理士)で、働く人のメンタルヘルスを専門としています。特に、新人看護職員のリアリティショックや看護現場におけるメンタルヘルス対策に興味をもっています。
私は精神科病院に30年勤務し、うつ病、適応障害、パニック障害等の方のカウンセリングを行い、2016年に大学の臨床心理学科の教員になりました。
これまでの経験を活かし、継続してメンタルヘルス不調に陥った看護職員に対し、職場適応支援を実践しています。
公益社団法人日本看護協会(2024)の報告によると、新卒看護職員の離職率は10.2%(2022年度)ですが、私が関わっている病院(1182床)では、4.2%(2022年度)、3.4%(2023年度)で推移し、離職率を低く抑えることができています。
アメリカのメンタルヘルスサービスEAP(employee assistance program:従業員支援プログラム)との出会い
私がかつて勤務していた精神科病院では、元理事長が過労死や過労自殺をされた方の裁判の意見書を書いていました。
働く人が悲しい結果にならないためには、予防としてのメンタルヘルス対策が必要ということで、2003年に精神科病院内に企業のメンタルヘルス支援を行う部署として、アメリカのメンタルヘルスサービスであるEAP(employee assistance program:従業員支援プログラム)の部門を立ち上げました。
このEAPの仕組みは、病院や企業と年間契約料をもらって契約し、そこの病院や企業の職員はメール相談・電話相談・カウンセリングが無料になるというものです。
職員は、悩みができた際に早めに相談することで、パフォーマンスを落とすことなく仕事を続けられるメリットがあります。
アメリカでは、フォーチュン誌が、全米の企業を収入に基づき上位500社をランキングしていますが、そのうちの90%の企業がEAPを導入しているようです。また、アメリカではEAPを提供する企業の数も12,000社を上回るといわれています。
現在、日本でもEAPを提供する企業は数多くあります。
最近、感じる世代間ギャップのストレス
Z世代(諸説ありますが、10歳代~20歳代前半)と呼ばれる若者世代が入職してくるようになりました。
これまでゆとり・さとり世代(おおむね20歳代~30歳代後半)等、世代間のギャップを感じることはありましたが、より付き合い方が難しくなっているように感じます。
Z世代は、生まれた時からインターネットやデジタル機器があった世代で、ベテラン世代のようなアナログ時代を知りません。
先日も、“見て習え”の教育を“パワハラ”と誤解した新人看護職員の対応をしてきました。
ベテラン世代は、自分が受けた“見て習え”の教育を当然のように若者世代にするわけですが、私が新人看護職員200名の研修で「“見て習え”という教育方法を知っている人?」と質問したところ、知っていたのは13名でした。
いつの間にか時代が移り変わり、“見て習え”を知らない人のほうが多くなっていました。
最近の職場では、このようなどちらが悪いというわけではないコミュニケーションのズレや誤解が発生し、お互いがストレスを感じる出来事が増えているようです。
予防するためには、事前に“見て習え”の教育方法とはどういうものかを入職時の研修の中で解説しておくことも、ひとつのやり方だと思います。
連載に向けて
どの年代の看護職員も、職場不適応を起こす時代になってきました。
看護管理者がその対応に追われ、日常業務が回らなくなることは大きい損失と考えます。
連載では、実際にあった事例を複数集め、架空事例として紹介し、対応例をお伝えしようと思っています。
エビデンスを含んだ対応を参考にしていただきながら、各病院でアレンジし、柔軟に活用していただければ幸いです。
(初出:『イマドキの若者解体新書 新人を看護にコミットさせるワザ』ナーシングビジネス2025年4月号より改変)
引用・参考文献
1) 谷原弘之.今どきナースが育つ支援体制と個別対応.名古屋,日総研出版,2020,200p.
………………………………………………………
【次回予定】第2回「イマドキの若者(Z世代)の特徴、向き合い方」です。お楽しみに!
『イマドキの若者解体新書 新人を看護にコミットさせるワザ』(Nursing BUSINESS(ナーシングビジネス)2025年4月号第1特集立ち読みより)

谷原 弘之(たにはら・ひろゆき)
川崎医療福祉大学医療福祉学部臨床心理学科 教授
公認心理師・臨床心理士。職場のメンタルヘルスサービスであるEAP(Employee Assistance Pro-gram:従業員支援プログラム)を実践し、病院・企業などを対象にメンタルヘルス研修、復職支援などを手掛ける。看護現場でのメンタルヘルス対策に関しても積極的に支援している。