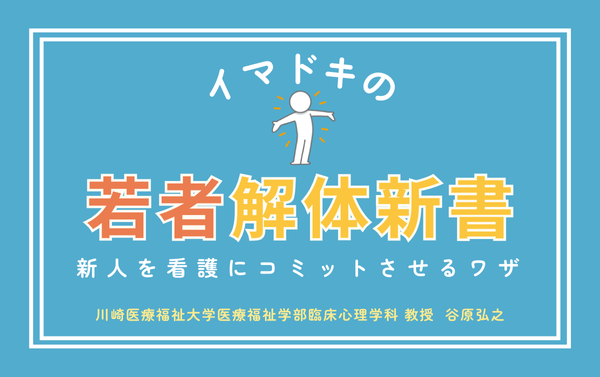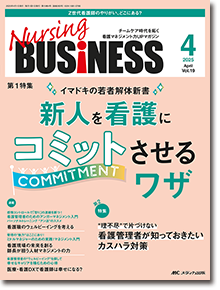イマドキの若者解体新書:
新人を看護にコミットさせるワザ_第3回
新人看護職員が入職し、少しずつ職場に慣れてきている時期だと思います。
今年の新人は、大学卒業者であれば1年生のときにコロナ禍の影響を受け、一時的にリモート授業を受けた可能性がある年代ではないかと思います。
少なからず対面でのコミュニケーションが制限されたことにより、自宅でゲームをしたりYouTubeを観たりして過ごす時間が長くなり、空想を伴う“推し”との世界に没入した人もいるかもしれません。
このため今年の新人は、入職してリアルな社会の現実に直面し、戸惑っている場合があるかもしれません。
【20歳代・女性の例】
看護師への動機づけが曖昧なまま就職し不適応
Aさんは、小さい頃から母親の顔色を見て行動するところがありました。
母親の喜ぶ顔が見たくて勉強を頑張り、高校のときは学年でも上位の成績を維持してきました。
大学へ進学するときも、母親から「看護師がいいんじゃないの」と言われたときに、他にやりたいこともなかったので、母親に勧められるまま看護系の大学に進学しました。
勉強は楽しかったのですが、実習へ行くようになると、実習指導者の指示にうまく対応できず、落ち込むことがありました。
自分は看護師に向いてないのだろうかと考え、時に眠れないことがありましたが、今さら進路変更もできず、卒業して実習先だった病院へ就職しました。
就職してからは、プリセプターの先輩から厳しく指導されるのが苦痛で、ストレスから腹痛で仕事を休むことがありました。
仕事を辞めて逃げ出したい気持ちと、母親を悲しませたくない気持ちで葛藤し、どうしていいかわからなくなりました。
それでも頑張ってやっていこうと思ったのですが、ある朝突然体が動かなくなり、それ以来、家から出られなくなりました。
現状の分析
近年はAさんのように、自分の意思ではなく家族の勧めで進路(看護師)を選ぶ学生も増えている気がします。
入職後数カ月経つと、いろいろなかたちで不適応が起こりますが、Aさんの場合、不適応となった際に早急に母親が退職を認めてしまうと、引き留める余地がなくなります。
したがって辞めそうな気配を感じた場合はスピード感をもって動くことがよいと思います。
対応の具体例
まず、ゆっくり休養することを勧めつつ、学生時代に楽しかった看護の内容を思い出してもらいましょう。
それがたとえば実習時の高齢者との会話であった場合は、学生時代に実習した病棟へ一時的にでも異動させ、自信を回復させましょう。
少しでもやりがいを感じることができれば、退職を思い留まるかもしれません。
………………………………………………………
【次回予定】第4回「リアリティショックからの回復が遅れがちなタイプへの支援ついて」です。お楽しみに!
「イマドキの若者(Z世代)の特徴、向き合い方」(イマドキの若者解体新書:新人を看護にコミットさせるワザ_第2回)

谷原 弘之(たにはら・ひろゆき)
川崎医療福祉大学医療福祉学部臨床心理学科 教授
公認心理師・臨床心理士。職場のメンタルヘルスサービスであるEAP(Employee Assistance Pro-gram:従業員支援プログラム)を実践し、病院・企業などを対象にメンタルヘルス研修、復職支援などを手掛ける。看護現場でのメンタルヘルス対策に関しても積極的に支援している。