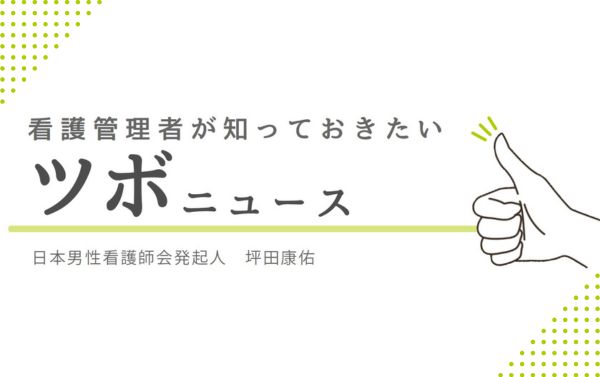看護管理者は日々多くの業務に目配り・気配りが必要です。国の施策や看護界を取り巻く状況、日々の働き方や組織づくりに関連した情報など、看護管理者が知っておきたい最新ニュースをご紹介します。
前回に続き、今回も看護の可能性が広がるニュースをお届けします。
今回は、①テクニカルショウヨコハマ2025、②健康経営フェスティバル、③健康博覧会2025/介護・高齢者福祉展の3つを取り上げます。
①テクニカルショウヨコハマ2025
2025年2月5~7日に横浜で開催された「テクニカルショウヨコハマ2025」に足を運んできました。
神奈川県などが主催するこのイベントは、「技術を創る 未来を創る」というテーマのもと、さまざまな企業の技術や革新的な取り組みが紹介されていました。
一見すると「技術展示会」という場は看護分野とは縁遠いように思えるかもしれません。
しかし、会場を歩く中で、看護の現場にも役立つ技術が紹介されており、とても興味深い発見がありました。
とくに印象に残ったのが、セミナーで紹介されていたKOBE-OLIVE株式会社の「VR(仮想現実)を活用した看護教育教材」です。
同社は、コロナ禍で看護学生が十分な実習を行えなかった時期から、学生の学びの機会を少しでも確保しようと、神戸大学が研究開発したVR教材を取り扱い、提供しています。
今回の展示ではその教材の中でも、AED(自動体外式除細動器)の使用法を学ぶための「急変対応のVR教材」が紹介されていました。

日本はAEDの設置率が世界トップクラスでありながら、実際に活用される場面が少ないという課題があります。
AEDを目の前にしても「使い方がわからない」「誤操作が怖い」と感じる人は少なくありません。
そうした状況を解決するために、このVR教材では看護学生が臨場感あふれるシミュレーションを通じてAEDの使用法と急変対応スキルを効果的に学べる仕組みがつくられています。
この教材は看護学生に限らず、一般の人々にも提供されており、それが今回セミナーで紹介された理由の一つとなっています。
同教材は、たとえばタワーマンションやショッピングモールといった、救急車が現場に到着するまでに時間がかかりがちな場所で働く警備員や管理人が学習する場面を想定しているそうです。
それにより、医療関係者以外の人でも救命に積極的に関われるようになるという点で、大きな可能性を秘めているといえます。
今回の展示を通じて、看護教育の教材が看護職という枠を越え、より多くの人々の命を守るためのツールとして活用され始めていることを強く実感しました。
「看護の知識や技術を社会全体で共有する」という新たな時代の流れを感じつつ、看護師として、また社会の一員として、私たちがこうした取り組みにどう関われるのかを考えさせられました。
また、このイベントでは、医療産業廃棄物を一般廃棄物へと変えることで、CO2排出量を削減する革新的な廃棄物処理方法を提供している株式会社マクニカの方とも出会うことができました。
同社の技術を活用することで、病院が抱える医療産業廃棄物にかかるコストを大きく削減できるだけでなく、環境に優しい医療を行う「Green Medicine(グリーンメディスン)」としての貢献が可能になるとのことです。
医療現場が抱える経済的負担と、地球環境への配慮という2つの課題を同時に解決する取り組みは、本当に素晴らしく、深く感動させられました。
②健康経営フェスティバル
2025年2月19日、産業看護師であり株式会社メディカルヘルスオンラインの代表を務める加瀬美郷氏が主催するフェスティバルに参加しました。
今回が2回目となり、港区からの後援も得て、前回よりも規模を拡大して開催されていました。
加瀬氏は、産業看護師として企業ごとの活動だけでは日本全体の活性化には不十分だという強い信念から産業看護の会社を創業し、多くの企業の健康管理を支援する活動を展開しています。
その視野はさらに広く、産業医の選定が義務化されていない中小企業にも健康経営の恩恵を届けたいという思いから、中小企業向けの産業看護サービスを提供する企業を集めたフェスティバルを企画したそうです。

このような取り組みを目の当たりにして、筆者は、厚生労働省看護課長から日本看護協会会長を務めた久常節子氏がよく語られていた「看護には三段階ある」という言葉を思い出しました。
三段階の第一段階は患者個人へのケア、第二段階はその家族と地域へのケア、そして第三段階は国全体へのケアです。
産業看護の現場では、このような段階的な視点が実践されています。
たとえば、ある製造業の現場では、個々の従業員の健康相談に応じるだけでなく、職場環境全体の改善や家族も含めた健康教育プログラムを実施することで、地域全体の健康意識向上につながった事例があります。
そのような取り組みが複数の企業に広がることで、国全体の労働生産性向上や医療費削減に寄与することになります。
加瀬氏の活動は、まさに看護の可能性を広げる実践といえます。
一人の看護師が自らの専門性を活かして起業し、その視野を中小企業全体、そして日本社会へと広げていく姿は、私たち看護職が進むべき道の一つを示しているように感じます。
③健康博覧会2025/介護・高齢者福祉展
2025年2月26~28日、東京ビッグサイトで「健康博覧会2025」や「介護・高齢者福祉展」など、ヘルスケアに関する展示会が開催されました。
会場では、看護師が支援するメディカルフーズの会社や遠隔看護の会社など、病院から飛び出し多岐にわたる分野で活躍する看護師たちの姿が見られ、看護師の活動領域がまさに広がっていることを実感しました。
中でも印象的だったのは、看護師によって立ち上げられた遠隔みまもり看護株式会社のブースです。
同社は、遠隔で看護師が支援するというサービスに加え、病院では当たり前の離床センサーを自宅に提供するなど、看護サービスを軸に患者を支援するさまざまな仕組みを構築してきました。
介護サービスにおいては、施設から在宅への移行が進んでいますが、離床センサーなどの病院で使用されるような機器が自宅に導入されるケースはまだ少ないのが現状です。
同社は、看護の専門性を活かしながら、最新のテクノロジーを駆使して解決しようと挑戦しています。
たとえば、高齢者が自宅で一人暮らしをする場合、夜間の転倒や急変は大きなリスクとなります。
離床センサーを導入することで、万が一の際には提携している訪問看護師が迅速に対応することが可能になります。
これにより、高齢者は安心して自宅で生活を続けることができ、家族も安心して見守ることができます。
*****
看護の専門性を活かしながら、テクノロジーやビジネスの知識を組み合わせることで、より多くの人々が安心して暮らせる社会の実現に貢献できるのではないでしょうか。
筆者はこれからも、看護の可能性を広げる活動をする方々を積極的に取材し、皆さんに情報をお届けしたいと考えています。
皆さんの施設でも、地域との連携や一般の方々への健康教育などで活用できる看護の知識や技術があるかもしれません。
ぜひ、日々の業務の中で「これは病院の外でも役立つのでは?」という視点を持っていただけたらと思います。
私たちの専門性は、想像以上に社会に求められているのですから、遠慮せずにその価値を広げていきましょう。
看護の可能性を広げる取り組みがあれば、ぜひこの連載でも取り上げたいと思いますので、編集室までお知らせください。
ご連絡先はこちら
※ 「その他」を選択し、お問合せ内容欄に「看護の可能性を広げる取り組み」とご記載ください。
引用・参考文献
1) テクニカルショウヨコハマ2025(第46回工業技術見本市).https://www.tech-yokohama.jp/(2025年3月26日閲覧)
2) 健康経営フェスティバル.https://www.kenkoufes.com/(2025年3月26日閲覧)
3)健康博覧会2025.https://www.this.ne.jp/(2025年3月26日閲覧)
4)介護・高齢者福祉展.https://www.care-show.com/mcs/(2025年3月26日閲覧)

坪田康佑(つぼた・こうすけ)
慶應義塾大学看護医療学部卒。Canisius College(米国ニューヨーク州)卒/MBA取得。無医地区に診療所や訪問看護ステーションを開業し、2019年全事業売却。国家資格として看護師・保健師・国会議員政策担当秘書など、民間資格ではメディカルコーチ・M&Aアドバイザーなどを持つ。
現在は国際医療福祉大学博士課程在籍、看護師図鑑(https://cango.blog/)を運営。
▼出典元:Nursing BUSINESS 2025年6月号