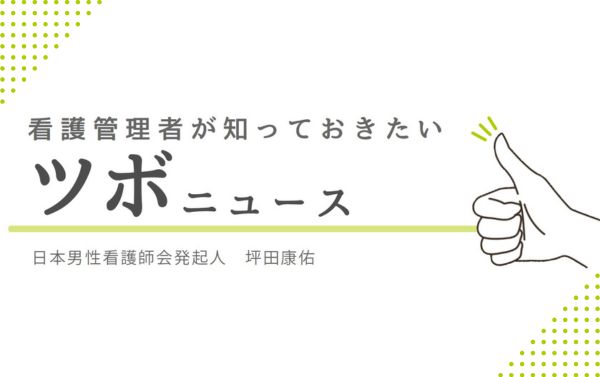看護管理者は日々多くの業務に目配り・気配りが必要です。
国の施策や看護界を取り巻く状況、日々の働き方や組織づくりに関連した情報など、看護管理者が知っておきたい最新ニュースをご紹介します。
日本看護協会通常総会・職能別交流集会より
2025年6月11日、12日の2日間、令和7年度日本看護協会通常総会および2025年度全国職能別交流集会が開催され、1,000人を超える看護職が一堂に会しました。
今年の総会は今後の私たちの働き方を考えるうえで非常に重要な意味を持つものでした。
2015年から掲げられてきた「看護の将来ビジョン2025」が最終年度を迎え、新たに「看護の将来ビジョン2040~いのち・暮らし・尊厳をまもり支える看護~」が発表されたからです。
看護師の役割は少しずつ、しかし確実に変化し、その多様性は広がり続けています。
私たち看護師の意見を最も集約している日本看護協会が目指す「看護の将来ビジョン2040」を把握しておくことは、まさに私たち自身の未来の働き方を考える貴重な機会となるでしょう。
2040 年に向けた看護の変革
このビジョンでは、2040年に向けた看護の変革として、以下の3つの目標が掲げられています。
①その人らしさを尊重する生涯を通じた支援
一人ひとりの価値観や人生観を尊重し、胎児期から看取りまで、その人らしい生き方を支える看護を提供することを目指します。
②専門職としての自律した判断と実践
技術革新が進む中で、看護職が自らの専門性を発揮し、予測される状態変化に対し自律的に対応できる能力を高めることを重視しています。
③キーパーソンとしての多職種との協働
看護職があらゆる機関に存在するという強みを活かし、施設や行政の垣根を越えて多職種連携のコーディネートを担い、地域の人々の健康な暮らしを支えるキーパーソンとしての役割を果たすことが求められます。
また、このビジョンではこれらの目標を実現するための、次のような戦略も示されています。
- 質の高い看護実践のための教育制度改革(看護師基礎教育の4 年制化など)
- より高い自律性を持った専門職としての活躍の推進(特定行為研修を修了した看護師の活躍促進など)
- 地域における看護の拠点の確保(訪問看護ステーションの大規模化や新たな看護拠点の創造など)
さらに、看護職が活躍するための基盤として、看護職一人ひとりのウェルビーイングの重視、自己研鑽と主体的なキャリア形成の推進、そして多様で柔軟な働き方への転換(夜勤負担軽減やキャリア継続支援など)が強調されています。
「看護の将来ビジョン2040」は、私たち看護職がこれからも「いのち・暮らし・尊厳をまもり支える看護」を提供し続けるための、道しるべになると思います。
日本看護協会の新体制
今回の通常総会では、新たな体制も発表され、第15代日本看護協会会長として、秋山智弥氏が選任されました。
これは初めての男性看護師の会長就任となります。
他業界では女性初の役職が話題になることがありますが、看護業界では逆の状況です。
このニュースからも、看護職が性別にかかわらず、その専門性を発揮し、リーダーシップを担う時代へと着実に歩みを進めていることがうかがえます。
看護の未来を語り合う「職能」の集い:全国職能別交流集会
日本看護協会総会とあわせて開催された「全国職能別交流集会」について説明します。
私たち看護職には、保健師、助産師、そして病院(看護師Ⅰ)や地域で働く看護師(看護師Ⅱ)といった専門性の異なる「職能」があります。
職能とは、簡単に言えば、それぞれの専門分野や働き方に応じた集まりのことです。
この「全国職能別交流集会」は、その職能ごとに、あるいは職能の枠を越えて一堂に会し、各分野における課題や現状、そして未来について深く議論し、意見を交換する場です。
たとえば、病院の看護師であれば、病院看護に特化した課題や新たな看護提供方法について話し合い、保健師であれば、地域における健康課題や多職種連携のあり方など、それぞれの専門領域の視点から看護の発展を目指します。
個々の看護師が日々の業務の中で感じる課題や疑問は、同じ職能の仲間と共有することで、より大きな視点で見つめ直し、解決の糸口を見出すことができます。
また、他の職能の看護師との交流を通じて、自身の専門性を客観的にとらえたり、新たな連携の可能性を発見したりすることも可能です。
職能別交流集会では、今年は6月12日の午前の枠を使って三職能合同交流集会が開催されました。
これは、看護職が一丸となって同じ未来を描けるようにとの思いから企画されたと考えられます。
各職種の2040年に向けた展望が語られ、それぞれの職域がどのように変化し、未来を築いていくのか、その方向性が共有されることで、より一層の連携と協働が期待されます。
「 全国看護師交流集会Ⅰ病院領域プログラム」より
職能別交流集会の午後の部について、ここでは「全国看護師交流集会Ⅰ病院領域プログラム」を中心にレポートします。
シンポジウムは、「2040年の看護を担うあなたに伝えたい看護のこと」というテーマで立場の異なる3名が登壇されました。
患者の立場として樋口麻衣子氏(富山AYA 世代がん患者会Colors 代表)、看護実践者の立場として野村仁美氏(独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター看護部長)、看護管理者の立場として川﨑つま子氏(大坪会グループ看護局長)の話には、立場が違えども共通のメッセージがあり、一連のつながりができあがっていました。
樋口氏の話はとくに印象的でした。
樋口氏は自身もがんサバイバーの当事者でありながら、がんCNSナースとしての専門性も持っています。
さらに、がんに関するアドボカシー活動を精力的に展開し、厚生労働省の検討会委員も歴任しています。
看護職の働き方は、時に法律や制度によって制限されることがありますが、樋口氏はその法律や制度に直接働きかけることで、看護の可能性を大きく広げていました。
私たち看護師は誰もが患者の立場になる可能性があります。
樋口氏が示した、「患者の視点からアプローチすることで看護の可能性が広がる」という事実は、まさにナイチンゲールの「病気になったら病人として看護を学ぶ」という名言を想起させるものでした。
たとえば、日々の現場で「もしこの制度があれば、もっと患者の支援ができるのに……」と感じることはありませんか。
樋口氏のように、患者の声を制度に届けることは、「私たち看護師が関わる医療環境そのものを改善できる道がある」ということを明確に示してくれました。
この活動は、個々の患者のケアにとどまらず、より良い医療システムを構築していくうえで、私たち看護職が果たすべき重要な役割の一つであると、あらためて認識させられました。
続いて野村氏からは、時代が変わっても決して譲ることのできない看護の本質と、それに対し柔軟に対応すべき実践として、看護記録の音声入力やタスク・シフトに関する具体的な取り組みについて話がありました。
看護記録の音声入力についてはトライアルから導入を決断、「記録時間の短縮だけでなく質も担保できる」「最先端の技術を活用し、人間にしかできないケアにより時間を使えるようにしたい」といった現場の声が上がったそうです。
また、音声入力によってその場で記録を行うことで、看護記録のリアルタイムな更新と連続性が実現できることが導入の決め手となったとのことでした。
また、タスク・シフトについては、「リスクが少なく、一定量が見込める仕事からタスク・シフトし、成功事例を積んでいく」というアプローチが非常に参考になりました。
タスク・シフトする職種の採用に関する試行錯誤の話も、まさに今、タスク・シフトを導入したいけれど、どこから手をつければいいのか悩んでいる現場にとって、実践的なヒントが満載でした。
最後に、川﨑氏の話ではスポット雇用の活用について前向きに話していた点が印象的でした。
訪問看護の領域では、「chokowa」などの看護師のスポットバイトマッチングサービスが普及してきていますが、病院での活用はなかなか進まないという話を耳にしていました。
しかし、川﨑氏の話を通じて、看護管理の考え方次第で、病院においてもスポット雇用を有効活用できる可能性が大いにあることがわかり、大変示唆に富む内容でした。
***
引用・参考文献
1) 日本看護協会.看護の将来ビジョン2040~いのち・暮らし・尊厳をまもり支える看護~.
https://www.nurse.or.jp/home/assets/vision2040.pdf(2025年8月27日閲覧)

坪田康佑(つぼた・こうすけ)
慶應義塾大学看護医療学部卒。Canisius College(米国ニューヨーク州)卒/MBA取得。無医地区に診療所や訪問看護ステーションを開業し、2019年全事業売却。国家資格として看護師・保健師・国会議員政策担当秘書など、民間資格ではメディカルコーチ・M&Aアドバイザーなどを持つ。
現在は国際医療福祉大学博士課程在籍、看護師図鑑(https://cango.blog/)を運営。
▼出典元:Nursing BUSINESS 2025年11月号