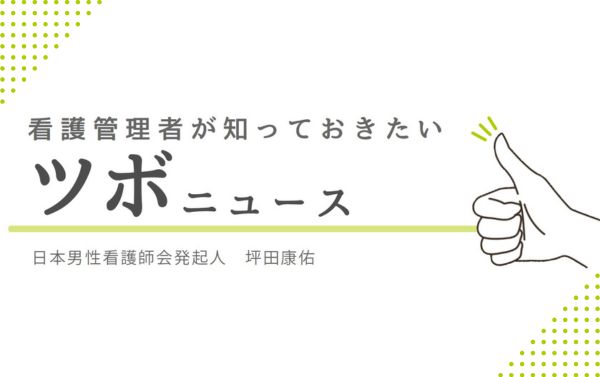看護管理者は日々多くの業務に目配り・気配りが必要です。国の施策や看護界を取り巻く状況、日々の働き方や組織づくりに関連した情報など、看護管理者が知っておきたい最新ニュースをご紹介します。
「看護師の仕事って病院内がほとんどでしょ?」 そう思っているのは、患者だけでなく、看護関係者の中にも少なくないかもしれません。
確かにこれまでは病院やクリニックが中心でした。
しかし現在は訪問看護師、スクールナース、施設看護師、産業看護職、ツアーナース、イベントナースなど看護職の活躍の場は多岐にわたっています。
また、病院における実践と研究は以前から密接に進められてきましたが、病院の外、つまり地域住民の健康づくりやイベントでの救護といった分野では、実践はされていても研究とは距離がありました。
せっかく実践している看護職の仕事の価値が不明確なのは、非常にもったいないことです。
とはいえ、「地域で看護の研究や実践をするなんて、具体的にどうすればいいの?」と感じるのも当然です。
そこで大きく期待できるのが、2025年春に開設された、東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター(東大GNRC)による新たな研究施設です。
筆者は、その完成見学会に足を運び、直接「新たな看護の波」を感じてきました。
新たな「拠点」が拓く看護の未来
東大GNRCは、東京大学医学部附属病院分院跡地である文京区目白台に「東大GNRCオープンラボ」を開設しました。
非常にざっくりいえば、これは「看護や公衆衛生に関する研究と実践を、地域の人々と一緒に進めていくための新しい『拠点』ができた」ということです。

そこでは、東京大学の看護関係者が力を合わせ、以下の3つに取り組んでいくそうです。
【取り組み1:暮らしの保健室】
地域住民を対象とした、相談、学び、安心、交流、連携、育成の場です。
平日の昼間は市民に開放され、相談や交流の場となることを目指します。
【取り組み2:みんなのケアする力をサポート】
ケアを受ける人も、ケアをする人もハッピーになることを目指し、ケアについて皆で教え学び合う場を提供します。
これは、子どもから高齢者まで、幅広い世代のケアに関する知識や技術を獲得するためのワークショップなどを指すと考えられます。
【取り組み3:看護・ケア専門職のサポート】
ケア関連職が互いに支え合い、支援できる場を提供します。
看護職や介護職など、地域で活躍する専門職が連携し、学びを深め、サポートし合えるようなプログラムや交流の場をつくります。
見学会での体験
見学会は、まるで看護学校の文化祭と学術的な学会が融合したかのようで、学びと発見に満ちた時間でした。
家族マネジメントプログラムやインクルーシブ教育の紹介から、AIアシストエコーや肌バリア評価といった最新の看護アセスメントデバイス体験、中高生向け看護師体験プログラムの紹介まで、多岐にわたる研究と実践が紹介されました。
さらに、赤ちゃんの股関節ケア研究やおむつ・エコー体験、妊娠・出産・育児に関するプログラムと赤ちゃん人形抱っこ体験など、母子看護に関する具体的な取り組みも展示されていました。
心の健康支援としてリカバリーカレッジやトラウマリカバリーの紹介もあり、地域に根差したケアの重要性が示されました。
一般社団法人東大看護学実装普及研究所によって開設された訪問看護ステーション「東大看護ステーション目白台」の紹介も行われ、地域に密着した未来志向の看護実践が具体的に示されました。
また、人生の最期を考えるカードゲームや心音を聴く体験など、楽しみながら生命や健康について深く考えることができるユニークな企画も魅力的でした。
この見学会は、最先端技術から地域ケア、次世代育成まで、多角的な視点から「看護」をとらえ直す機会でした。
筆者に限らず参加者一人ひとりが、看護の無限の可能性と、未来への希望を感じられたのではないかと考えます。
地域に根ざした看護の可能性
2024年11月には、GNRCと文京区が連携協定を締結しました。
GNRCが入居するビルにはクリニックや高齢者施設が併設され、地域におけるケア医療の普及の拠点となることを目指しています。
院外で生まれ続ける新たな看護の役割を研究し、実践していく場ができたというのは、本当に画期的なことです。
これまでは「病院外での看護師の役割は漠然としている」と感じていた人も多いと思いますが、これからは具体的な研究と実践を通して、その可能性が広がっていくことになります。
オープンラボでは地域住民を対象としたイベントも多数開催されており、予約でいっぱいになるほどの盛況ぶりだそうです。
これは、地域住民の看護や健康への関心が高いことの表れであり、オープンラボがすでに地域に受け入れられている証拠だと思います。
一般的に、地域活動の難しさの一つに、立ち上げ当初は目新しさから多くの人が集まっても、時間が経つにつれて活動が形骸化することがあります。
しかし、このオープンラボが研究と結びつき、明確な成果を出し続けていくことで、その活動は持続性を持ち、地域にとって不可欠な存在へと成長していくはずです。
「家族まるごとケア」という新モデル
さらに注目すべきは、オープンラボのすぐ近くに開設された、前述の「東大看護ステーション目白台」です。
これは、超高齢・人口減少社会を迎える日本において求められるイノベーションを開発し、実際に社会に実装していくという、まさに未来志向の取り組みといえるでしょう。
この訪問看護ステーションでは、従来の個人への看護提供にとどまらず、「家族のかかりつけ看護師」として世帯単位でのケアを目指しています。
とくに画期的なのは、月額制看護サービス(保険外サービス)として、世帯への定期訪問(自宅はもちろん、病院や介護施設など、どこへでも訪問可能)や遠隔相談(電話やメール)を受け付ける新たなサービスを構築している点です。
東大GNRCの研究者と連携し、乳幼児から超高齢者まで、最新の知見に基づいた質の高いケアを提供してくれるのです。
実際に終末期の訪問看護に携わっていると、本人だけでなく、家族の意向によって求めるケアが変化していくことを痛感します。
本人もまた、状況によって考え方が揺らぐことも少なくありません。
2024年、グッドデザイン賞を受賞した佛教大学の濱吉教授が作成したエンディングノート「わたしのいきかた手帳」も、本人の思考の「ゆらぎ」を記せるように開発されていました(本連載記事「看護師が開発した「わたしのいきかた手帳」濱吉美穂さんの挑戦とグッドデザイン賞」参照)。
このことからも、本人だけでなく、家族も含めて事前に深く対話を重ね、それぞれの価値観や意思を理解しておくことで、よりきめ細やかなケアが可能になると強く感じます。
家庭の中にお邪魔することで、患者個人だけでなく、その家族全体を深く理解できます。
それは「家族看護」の新たな幕開けになるのではないでしょうか。
診療報酬や介護報酬といった社会保障費の介入以前から訪問看護師が関わることで、単なる予防医療にとどまらず、効果的な保険サービスの活用方法や、保険サービスと保険外サービスとの効率的な連携を模索していくことが可能になると思います。
さらに、スタッフ全員が研究者でもあるため、その一つひとつの効果に関して、ただの事例に終わらせず、取り組みを通じて、日本の超高齢社会における訪問看護の新たなモデル形成につながることも大いに期待されています。
***
筆者自身、看護研究を率先して実施していた看護師ではないので、GNRC開設について知ったとき、ここまでの可能性を感じていませんでした。
しかし、実際に見学会に参加し、各研究者の挑戦と地域の受け入れ態勢から、「これこそ、看護職の新しいキャリアを切り拓く場所だ!」と興奮しました。
地域住民の誰もが、自分と自分のまわりの人たちを大事にできる「幸せ社会」を目指すというコンセプトにも、心から共感します。
看護師としての知識やスキルが、病院の中だけでなく、もっと多様なかたちで社会に貢献できる可能性を秘めていることを、GNRCの開設に始まる出来事は教えてくれているのではないでしょうか。
今まで考えもしなかった看護師の働き方があるのかもしれません。
まさに看護の未来を担う私たち看護師にとって、大きなヒントを与えてくれるものだと信じています。
病院での看護はもちろん大切ですが、地域社会に深く根ざし、人々の暮らしを支える看護職の役割も、これからますます重要になっていくはずです。
看護師としてのキャリアの選択肢は、私たちが思っているよりもずっと広いのかもしれません。
引用・参考文献
1) 東大看護ステーション目白台.https://mejirodai.utndi.or.jp/(2025年7月30日閲覧).
2) 東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター.https://gnrc.m.u-tokyo.ac.jp/(2025年7月30日閲覧).

坪田康佑(つぼた・こうすけ)
慶應義塾大学看護医療学部卒。Canisius College(米国ニューヨーク州)卒/MBA取得。無医地区に診療所や訪問看護ステーションを開業し、2019年全事業売却。国家資格として看護師・保健師・国会議員政策担当秘書など、民間資格ではメディカルコーチ・M&Aアドバイザーなどを持つ。
現在は国際医療福祉大学博士課程在籍、看護師図鑑(https://cango.blog/)を運営。
▼出典元:Nursing BUSINESS 2025年10月号