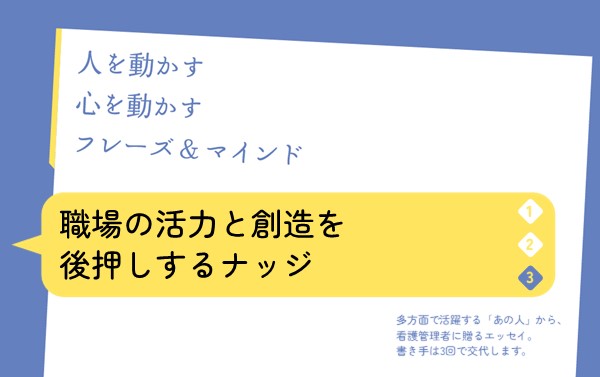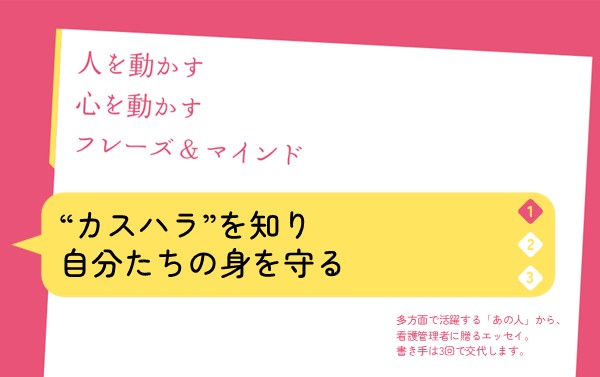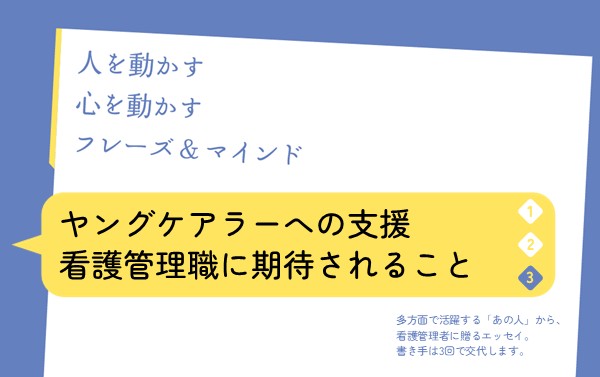私たちは日々職場の問題解決に奔走していますが、どんなに素晴らしい改善策でも職場の皆が実行してくれなければ成果は生まれません。
もし、望ましい行動がとれない原因が人の認知メカニズムや環境デザインに関連しているのであれば、ナッジは有効な解決策になる可能性があります。
人々の行動を変えるのは容易ではありません。
ロケットの打ち上げに例えて考えてみましょう。ロケットが宇宙空間に到達するためには、空気抵抗を極力減らすデザインや素材、そして十分な燃料が必要です。
職場でも行動変容を妨げている摩擦や抵抗の要素を減らし、いかに行動しやすくするかが鍵となります。「面倒」と感じさせるちょっとした手間が、行動の先送りやうっかり忘れを生じさせ、実施率を下げてしまうからです。
これには人が選択する際の負担を減らすデフォルト(初期設定)を活用すること、複雑な手順をより単純かつ明快にすること、メッセージの簡素化を図ること、誰もが自然に整理整頓してしまうような物の配置や動線をデザインするといった「簡単」で「すぐに」できるナッジが有効です。
また、行動変容を促すエネルギーを高めるナッジの併用も効果があります。
努力しなくても自然に目が向くようにアイキャッチの高い色やデザインの利用、心地よい称賛や褒美といったインセンティブは行動する「魅力を高める」ナッジです。
その行動が社会規範にかなっていることや、他者の役に立っていることを強調する「社会的」なナッジも人を後押しします。
ナッジは問題解決を補完する補助的な手法であり、ごく些細な働きかけに見えます。
しかし解決策の実行度が高くなり、労力に比して得られる効果が大きいことを実感している職場は多いことでしょう。
何より「シンプルで魅力的」を目指すナッジを使った対策は、多職種でアイデアを出しやすく、思わずうなってしまうユニークなものが続々と生み出され、楽しく活気ある取り組みとなります。
変化の激しい時代、前例のない課題に立ち向かっている日々の中で、看護管理者には組織の未来をつくる責務があります。しかし疲弊している現場からは新たな方策を創造する力は生まれません。
こころの「ゆとり」は熟慮や創発の土壌です。職場にさまざまな「ゆとり」を生み出し、活力と創造を引き出すナッジは、看護管理者の職場づくりにとっての大きな力になるでしょう。

小池智子(こいけ・ともこ)
慶應義塾大学 看護医療学部/大学院健康マネジメント研究科 准教授。看護学博士。専門は看護管理・看護政策。慶應義塾大学病院で13 年間、臨床や現任教育に従事。東京医科歯科大学大学院博士課程修了後、慶應義塾大学看護医療学部専任講師を経て、2007 年より現職。現在は主に行動経済学やデザイン思考を活用した医療安全や職場改革等に取り組んでいる。
▼出典元 Nursing BUSINESS(ナーシングビジネス)2023月12号
https://store.medica.co.jp/item/130212312
▼Nursing BUSINESS(ナーシングビジネス)トップページ https://store.medica.co.jp/journal/21.html