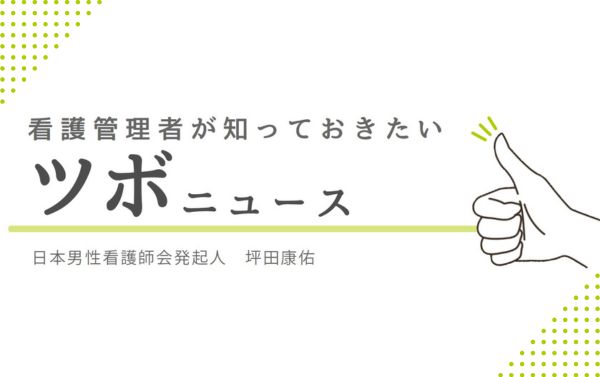看護管理者は日々多くの業務に目配り・気配りが必要です。国の施策や看護界を取り巻く状況、日々の働き方や組織づくりに関連した情報など、看護管理者が知っておきたい最新ニュースをご紹介します。
大盛況の「ナーシングデータサイエンス講座」
2025年4月15日、新たに東京大学に開設された「ナーシングデータサイエンス講座」の開設記念シンポジウムに参加してきました。
今回は“データサイエンスと看護のこれから”について、まさに熱気あふれる現場からレポートします。
シンポジウムは事前申し込みの段階で満席でした。当日は筆者も14階の会場へ向かうエレベーターを待つ長い列に加わることになり、「これほどまでに看護のデータサイエンス推進に注目が集まっているのか」と肌で感じました。
実際に当日の参加者は200名を超えていて、看護界の著名な方々の姿をたくさん拝見しドキドキする場でした。
日本看護協会は2025年1月1日に東京大学との連携講座を開設しましたが、この取り組みは職能団体として個々の看護師だけでは変えられない課題に対応し、看護問題解決のためのエビデンス構築を目指す重要な一歩です。
「 看護の可視化」「エビデンスの構築」を目指す
会場に着席すると、まず南學正臣氏(東京大学大学院医学系研究科長)、高橋弘枝氏(日本看護協会会長)による挨拶がありました。
続いて今回のプロジェクトの設置科目責任者である林田賢史氏(東京大学大学院医学系研究科社会連携講座ナーシングデータサイエンス講座特任教授)から講座開設の意義について説明がありました。
林田氏は、看護業界におけるサービス利用者および提供者の変化や財政状況の問題など多様化する課題に対し、看護の適正化を考えるうえで量的データを用いた研究が圧倒的に不足している現状を指摘しました。
また、看護師の貢献度や直面している課題を定量的に示すことができていないという問題意識のもと、この講座で「看護の可視化」と「エビデンスの構築」を目指すことを示しました。
具体的な活動としては、既存データの活用、複数のデータベースの結合、必要なデータの新規作成、そして定義の統一・標準化・記録の整備などを進めていくと説明しました。
「臨床、政策・行政、学術の連携で看護の可視化を加速する」という言葉が印象的で、講座だけでなく看護界全体での協力を呼びかける姿勢に、会場の参加者も熱心に耳を傾けていました。

Nursing-Sensitive Indicators(看護敏感指標)
続いて登壇した協力講座の池田真理氏(東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻看護管理学教授)からは、Nursing-Sensitive Indicators(看護敏感指標)について解説があり、看護の質が患者アウトカムの差にどう影響するかを測定することの難しさに触れつつ、このような取り組みは決して新しいものではないと指摘しました。
また、ナイチンゲールが戦時中の死亡原因をデータで示して政策に働きかけた史実や、ドナベディアンモデル、1995年頃に米国の看護協会で確立された10の指標などの歴史的背景が紹介されました。
とくに興味深かったのは、大卒看護師が10%増えると死亡率が4%減少するという研究結果や、看護師の増員が死亡率低下につながるという研究など、具体的なエビデンスの紹介でした。
日本における看護主導の取り組みとして、クリティカルパスや入退院支援センターの事例も語られ、遠い世界の研究ではなく身近な医療現場と照らし合わせながら聞くことができたと感じます。
さまざまな講演で盛り上がるシンポジウム
協力講座の康永秀生氏(東京大学大学院医学系研究科臨床疫学・経済学教授)からは、限られた時間ながらも濃密な内容の発表がありました。
ナイチンゲールによる統計分析の先駆的取り組みから始まり、リアルワールドデータとリアルワールドエビデンスについての解説へと進みました。
「認知症の重症度と褥瘡」「COVID-19パンデミック下のICU 患者の配偶者の精神疾患発症との関連」「要介護高齢者への人工呼吸器装着後の転帰」「夜勤看護師の配置改善と手術成績の関連性」など、実際の研究事例が次々と紹介され、ナーシングデータサイエンスの可能性の広がりを実感しました。
シンポジウムの後半では「ナーシングデータサイエンスの推進に向けて」と題した特別講演が習田由美子氏(厚生労働省医政局看護課看護課長)、武村雪絵氏(日本看護管理学会理事長/東京大学医学部附属病院看護部長)、中野夕香里氏(日本看護協会専務理事)という看護界の主要な3つの立場からの講演があり、今回設立された講座を活用した看護の未来についての展望が語られました。
そしてシンポジウムの締めくくりとなったのが「政策・臨床・アカデミアの協働で創るナーシングデータサイエンスの未来」というパネルディスカッ
ションでした。
協力講座の教授陣や特別講演の登壇者が一堂に会し、看護の未来を多角的に議論する場となりました。
このディスカッションでは、今まで築かれてきた看護の価値を、誰にでも通じるサイエンスに変換していく重要性が強調されました。
筆者自身、今回の議論を聞きながら、「今までそれぞれ違う道で山を登るように続けてきた看護の歩みが、このデータサイエンスという“共通言語”によって、さらに高い頂(=より良い社会や患者の笑顔)に近づけるのでは」という期待も感じました。
データサイエンスが苦手な人こそ関わるべき
会場を後にしながら、この新しい講座の設立が私たち看護師が長年直面してきた「目に見えない看護の価値」を可視化する大きな一歩になると確信しました。
現場の看護師として日々忙しい業務に追われる中で、こうした研究やデータ収集への協力は容易ではありません。
しかし、私たちの日々の実践があってこそ、看護の価値を示すエビデンスが蓄積されていくのだと思います。
正直に告白すれば、このシンポジウムに参加する前は気乗りがしていませんでした。
というのも筆者は、「データサイエンス」という言葉を聞くだけで構えてしまう看護師の一人でした。
そして日々の業務に追われる中で、難解な統計や分析などには到底手が出せないと感じていました。
「データなんて難しそう」「忙しくて勉強している余裕はない」「現場の実践と何の関係があるのだろう」という多くの看護師の素直な疑問や不安を筆者自身も共有していたのです。
しかし、このシンポジウムを通じて、データサイエンスは決して遠い世界の話ではなく、むしろ私たち看護師の日々の実践を裏づけ、価値を可視化する重要な武器になり得ることを学びました。
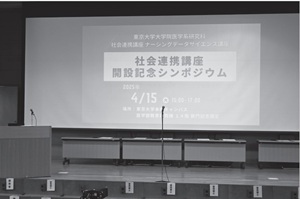
大切なのは高度な統計スキルではなく、自分たちの日々の実践の中にあるデータへの関心と、それを共有する姿勢なのだと気づいたのです。
限られた時間の中でも、わずかでも興味を持ち、自分の実践を振り返る視点を持つことが、看護の未来を切り拓く第一歩だと感じました。
*****
シンポジウムの内容はオンラインで公開されています。
看護の未来をデータの力で切り拓く新しい挑戦に、私たち一人ひとりが何らかのかたちで関わっていければと思います。
看護管理者の皆さん、この新たな流れをぜひ一緒に支えていきましょう。
| ●オンデマンド動画: https://tv.he.u-tokyo.ac.jp/course_12164/ ●シンポジウム・発表スライド: https://nds.m.u-tokyo.ac.jp/news/nds-ev-20250415/ |
引用・参考文献
1) 日本看護協会.東京大学と社会連携講座「ナーシングデータサイエンス講座」を開設.https://www.nurse.or.jp/home/assets/20250110_nl01.pdf(2025年6月5日閲覧)
2) 東京大学.東京大学と公益社団法人日本看護協会による社会連携講座「ナーシングデータサイエンス講座」を開設.
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400254562.pdf(2025年6月5日閲覧)
3) 日本看護協会.東京大学と社会連携講座「ナーシングデータサイエンス講座」開設記念シンポジウムを開催.https://www.nurse.or.jp/home/assets/20250401_nl01.pdf(2025年6月5日閲覧)
4) 東京大学大学院医学系研究科 社会連携講座.開設記念シンポジウム開催のお知らせ(2025 年4 月15 日).
https://nds.m.u-tokyo.ac.jp/news/news-455/(2025年6月5日閲覧)
5) 東京大学大学院医学系研究科 社会連携講座.ナーシングデータサイエンス講座 開設記念シンポジウムを開催しました.
https://nds.m.utokyo.ac.jp/news/news-1000/(2025年6月5日閲覧)
6) 東京大学大学院医学系研究科 社会連携講座facebook.
https://www.facebook.com/utokyo.nds(2025年6月5日閲覧)

坪田康佑(つぼた・こうすけ)
慶應義塾大学看護医療学部卒。Canisius College(米国ニューヨーク州)卒/MBA取得。無医地区に診療所や訪問看護ステーションを開業し、2019年全事業売却。国家資格として看護師・保健師・国会議員政策担当秘書など、民間資格ではメディカルコーチ・M&Aアドバイザーなどを持つ。
現在は国際医療福祉大学博士課程在籍、看護師図鑑(https://cango.blog/)を運営。
▼出典元:Nursing BUSINESS 2025年8月号