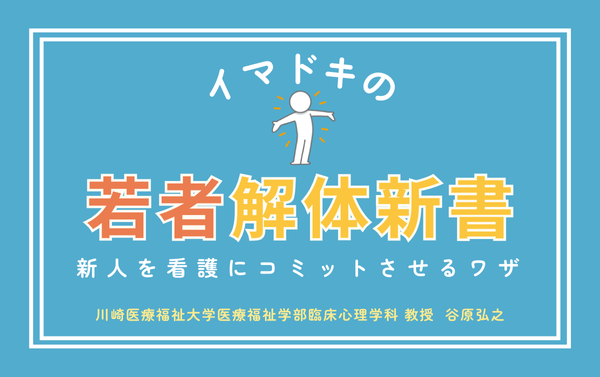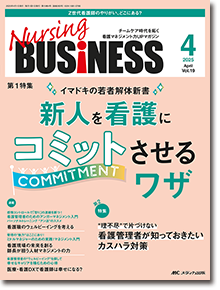イマドキの若者解体新書:
新人を看護にコミットさせるワザ_第5回
職場や学校において、発達障害とは診断されないものの、「場の空気が読めない」「こだわりが強い」といった発達障害の特性を感じる、いわゆるグレーゾーンの人がいると思います。
コミュニケーションがうまくとれず、周囲が疲弊することもあり、お互いにストレスを感じることがあります。
【20歳代・男性の例】
場の空気が読めない
Aさんは入職2年目です。
休憩時間に同僚3人と雑談をしていました。
同僚のBさんが「うちの看護師長は仕事が遅くて困るんです。先日、事務から電話があり、『患者さんの退院の書類を早く出してください』と、私が怒られました」と愚痴をこぼしました。
それを聞いたAさんは、看護師長のせいでBさんが困らされていると思い込み、急に立ち上がって看護師長のところへ行き、「看護師長、仕事をもっと早くしてください!」と抗議しました。
しかし看護師長は何のことかわからず、ポカンとしてしまいました。
Bさんも、自分が看護師長について愚痴を言っていたことが伝わってしまい、気まずい空気が流れました。
Aさんは、なぜこんな行動をとってしまったのでしょうか?
対応例(一例)
Aさんは場の空気が読めなかったため、同僚Bさんの発言が愚痴だとわからず、本当に困っていると思い込んで、正義感を持って看護師長に抗議に行ったと思われます。
場の空気を読む能力として「心の理論」というものがあります。
これは人間の発達段階で4歳~5歳頃に獲得でき、その後、成長とともに伸びてゆくとされています。
「心の理論」は、
①場の空気を読む能力
②相手の気持ちを察する能力
③見通しをつける能力 のことで、
コミュニケーションを行ううえで大切なものですが、自閉症スペクトラム障害(ASD)の特性がある人の一部には、大人になって「心の理論」がうまく機能しないことがあり、突拍子もない行動をとって周囲とトラブルになることがあります。
対応としては、以下の3段構えになります。
<第1段階>
「あなたは看護師長が書類を提出するのが遅いせいで、同僚Bさんが事務から怒られて困っていると思い、看護師長に抗議に行ったのですね」と、まず本人の行動を肯定で評価します。
Aさんが「その通りです」と答えた場合、次の段階に進みます。
<第2段階>
Bさんの発言は“愚痴”というものであることを伝え、“愚痴”は話を聞いてもらうことが目的で、具体的に看護師長に苦情を言ってほしいわけではないことを教えてあげます。
しかし、言葉の説明だけで“愚痴”を理解することが難しかった場合、第3段階に進みます。
<第3段階>
今後、休憩時間に同僚が仕事で困っている話をしていても、「〇〇のことで困っているので助けてください」と具体的に助けを依頼されない限りは、行動しないことを約束してもらいます。
このやり方の意図は、Aさんのマニュアルにある「困った人がいれば私が助けてあげよう」というものを、「困っている人が私に助けを求めてきた時だけ力になってあげよう」に書き換えることが目的です。
うまくAさんのマニュアルを書き換えることができれば、不適切な行動は減っていくと思います。
ASDのタイプの場合は、自分流のマニュアルを持っていることが多いです。
現場は大変かもしれませんが、場面ごとにその内容を表出してもらい、不適切であった場合は丁寧に修正をかけてあげることがよいと思います。
その際、いろいろな事例を提示して頭で理解してもらおうとすると逆に混乱が生じるため、シンプルにマニュアルを書き換える手法を試みることがおすすめです。
………………………………………………………
【次回予定】第6回「発達障害の特性への支援~注意欠如・多動性障害(ADHD)傾向の場合~」です。お楽しみに!
「リアリティショックからの回復が遅れがちなタイプへの支援」(イマドキの若者解体新書:新人を看護にコミットさせるワザ_第4回)

谷原 弘之(たにはら・ひろゆき)
川崎医療福祉大学医療福祉学部臨床心理学科 教授
公認心理師・臨床心理士。職場のメンタルヘルスサービスであるEAP(Employee Assistance Pro-gram:従業員支援プログラム)を実践し、病院・企業などを対象にメンタルヘルス研修、復職支援などを手掛ける。看護現場でのメンタルヘルス対策に関しても積極的に支援している。