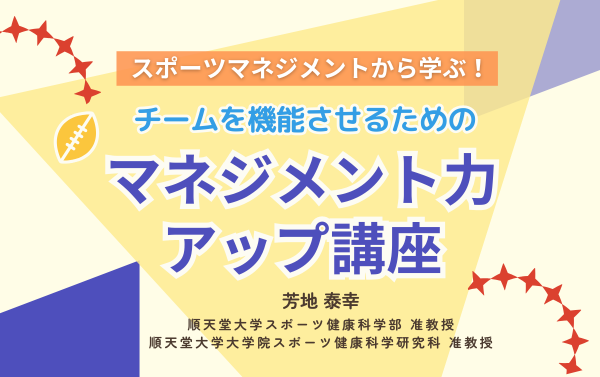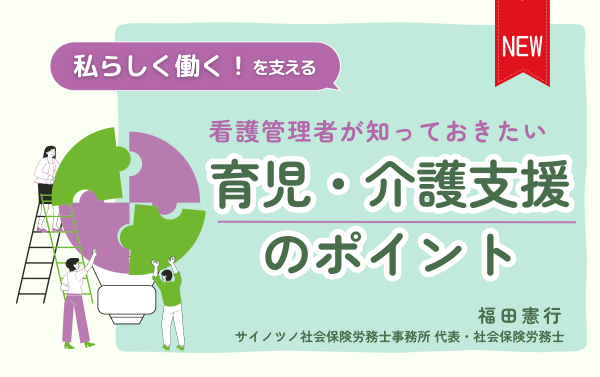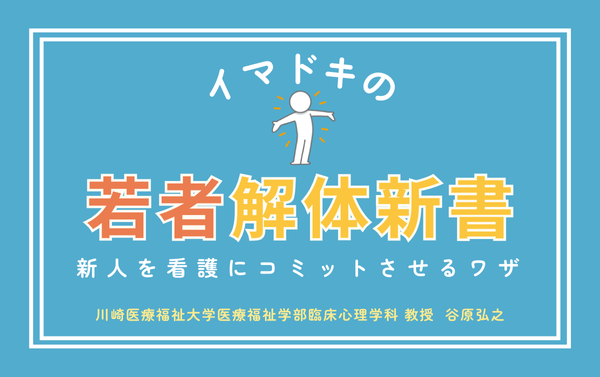スポーツマネジメントから学ぶ!
チームを機能させるためのマネジメント力アップ講座_第6回
スポーツチームと医療看護組織には共通点があります。
リーダーシップやモチベーション、チーム作り、次世代の育成など、看護の明日をより輝かせるためのヒントをお届けします。
人が育ち、辞めない職場をつくるために
「手塩にかけて指導したのに、辞めてしまった……」そんな声を、看護管理者から耳にする機会は少なくありません。
『看護師の「辞めたい」に耳をすます一離職防止に取り組む現場のリアル』1)からも92%の看護管理者が、看護師の離職を課題としてとらえている現状が浮き彫りになっています。
慢性的な人手不足のなかで日々の業務をこなしながら、新人や中堅スタッフの育成にも目を配らなければならない。
その重責と難しさに、思わず肩を落としたくなる瞬間もあることでしょう。では、スタッフが定着し、いきいきと働き続けられる職場をつくるためには、何が必要なのでしょうか。
近年注目されているのが「リテンション・マネジメント(Retention Management)」という考え方です。
これは、人材流出による損失を防ぎ、優秀な人材が組織にとどまり続けるための取り組み全般を指します。
民間企業を対象とした調査からは、退職率の低さが売上高や経常利益といった業績と関連していることが報告されており、リテンション・マネジメントの重要性が指摘されています2,3)。
しかも近年では、その内容も多様化しており、単なる福利厚生や能力開発にとどまらず、働き方改革やダイバーシティ、ライフステージに応じた支援など、広範で柔軟な対応が求められるようになってきています。
一方で、離職の背景には、「目指したいロールモテルが職場におらず、働くことがつらかった」「やりがいや成長している実感が得られなかった」「キャリアパスが見えない」といった、「キャリアのつまずき」が見え隠れしているのも事実です。
近年では、働くうえでの満足感や継続意欲の根底に「成長の実感」があることが報告されています。
パーソル総合研究所が実施した「働くl 0,000人の就業・成長定点調査」から、20代の正社員において成長実感が高まるほど、継続就業の意向も高くなる傾向が確認されています4)。
さらに、組織への総合的な満足度を左右する要因として、「自分の成長予感」と「貢献実感」が高い相関を示していることも報告されています5)。
すなわち、給与や勤務条件だけでなく、「この職場で成長できそうだ」「ここで働き続けたい」という実感やキャリアの見通しが得られることは、リテンション・マネジメントにおいてきわめて重要な要素になります。
このように、「人材の定着」と「キャリアの発達」は決して別々のテーマではありません。
むしろ、両者は深く結びついた同根のテーマであり、双方を同時に支えるマネジメントが今、看護組織に強く求められているのではないでしょうか。
管理職に求められるキャリア開発のまなざし
看護職のキャリアとは、単なる昇進やスキルの習得にとどまらず、「自分なりのやりがいを感じながら働き続けること」や「チームの一員としての貢献実感」など、より広い意味を持ちます。
その発達を支えるうえで、現場で最も身近な存在である師長や主任などの看護管理者との関わりがとても重要になります。
キャリア開発とは、特別な制度や新しい研修を導入することだけではありません。
むしろ日々の関わりの なかで、「このスタッフは今どんな状況にあるのか」「どんな看護師を目指しているのか」といった視点をもち、言葉をかけ、成長のきっかけを提供することが大切です。
ときに、技術を教えること以上に、「あなたのことを見ている」「成長を応援している」というメッセージを伝えることが何よりも力になります。
それは、スタッフの成長を願い、対話を惜しまない日々の積み重ねによって育まれていくものです。
特別な制度がなくても、 10分間の雑談、1枚のメモ、一言の承認が、スタッフにとっては大きな支えとなることでしょう。
このように、技術指導や業務連絡だけでなく、「自分のことを気にかけてくれている」「ここで成長できると思える」という実感が、職場へのエンゲージメントを高め、早期離職の抑止にもつながっていくのです。
それは、「あなたは、どんな看護師になりたい?」という、素朴な問いから始まる関わりともいえるでしょう。
自身のキャリアに向き合う姿勢が土台になる
スタッフのキャリアを支える管理者自身もまた、自らのキャリアを振り返り、内省し、再構築していくことが求められます。
近年、私たちの働き方やキャリア観は大きく変化しています。
従来のように「長く勤めること」や「決められた出世コース」が評価される時代から、「自分らしいキャリアを、自分で選び、築いていく時代」へと移行しています。
こうした時代のなかで注目されているのが、「キャリアの自律性(career autonomy)」という考え方です。
これは、自らの興味やスキル、価値観に基づき、自分自身で進むべき方向を考え、行動していくことを意味します。
「自分は何のために働くのか」「どんな環境で力を発揮できるのか」「どんなことにやりがいを感じるのか」といった問いに向き合い、勝ち負けではない「自分らしいキャリア」を築いていく姿勢が、今後ますます重要になります。
それが、部下にとって信頼できるロールモデルとなり、対話の質を高めるとともに、キャリア開発の本質的な出発点となるのではないでしょうか。
現代では働く目的が「組織のなかでの役割」から、「仕事そのものの価値」へ、そして「人生にとっての 意味づけ」へと広がっています。
そのような時代において、管理者はよきメンター(指導者)として、一人 ひとりの人生に丁寧に向き合う姿勢が求められています。
キャリア開発とは、誰かの未来を応援する営みであると同時に、支援する側自身の成長をも育む営みです。
管理者が自らのキャリアを育てる姿勢を持つことで、その背中が部下にとっての道しるべとなり、ともに育ち合う風土をつくる第一歩になるのではないでしょうか。
スポーツの世界でも「育てながら勝つ」ことは容易ではありません。
しかしその難しさこそが、リーダーとしての成長の機会であり、挑戦する価値のある営みなのです。
ともにこの難題に取り組んでいきましょう。
引用・参考文献
1)看謹管理サポートサイト.看誰師の「辞めたい」に耳をすます一離職防止に取り組む現場のリアル.つながる看護管理VOICE第3回目アンケート結果.
https://kango.medica.co.jp/archives/11065
2)山本寛.“人事労務担当者のためのリテンション・マネジメント一人材流出を防ぐ実践的アプローヂ’.東京,日本法令,2025, 232p.
3)山本寛.人材定着のマネジメントー経営組織のリテンション研究.東京,中央経済社,2009, 282p.
4)金本麻里.若手社員の成長実感の重要性ー若手の成長意欲を満たし、本人・企業双方の成長につなげるには.
パーソル総合研究所ウェプサイト.2020. https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/thinktank-column/202009090001/
5)カイラボウェプサイト.早期離職白書.2022. https://kailabo.com/soukirisyokuhakusyo2025_dl-2/
………………………………………………………
【次回予定】第7回は「もめことを乗り越える」です。お楽しみに!
芳地泰幸(ほうち・やすゆき)
順天堂大学スポーツ健康科学部准教授
順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科准教授(併任)
香川県生まれ。順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科博士後期課程単位取得満期退学後、聖カタリナ大学講師、日本女子体育大学准教授を経て現職。公益財団法人大原記念労働科学研究所協力研究員。マネジメントの視点から組織活性化や職場の創造性、リーダーシップ開発について研究している。博士(スポーツ健康科学)。
『チームワークとコミュニケーション』(スポーツマネジメントから学ぶ!チームを機能させるためのマネジメント力アップ講座_第5回)