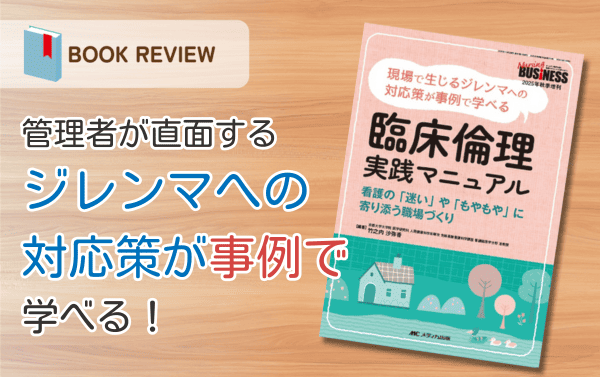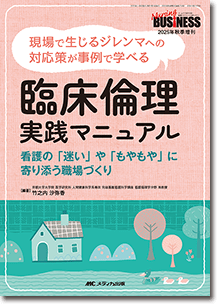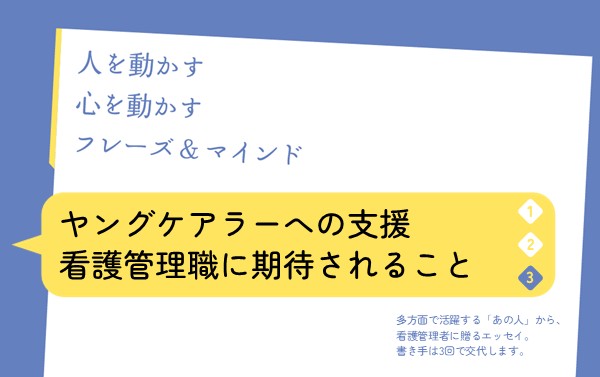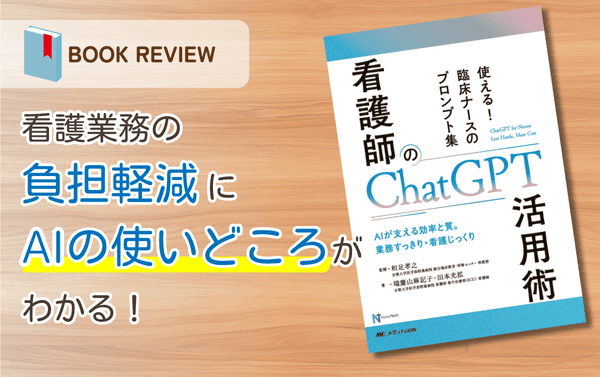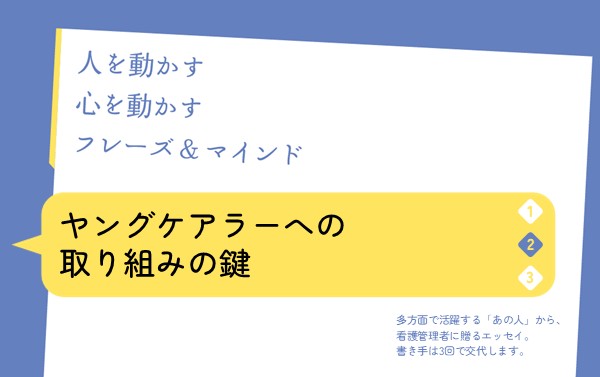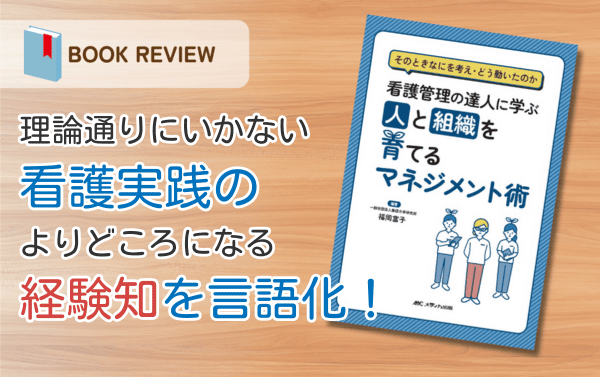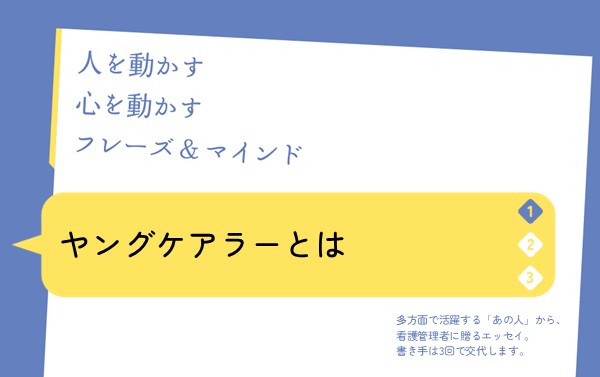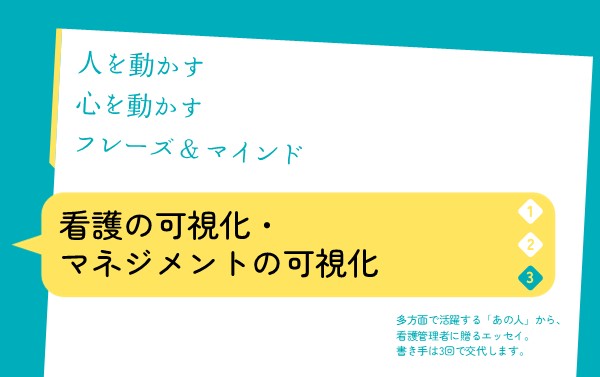タスクシフトシェアや医療DXの波が押し寄せ、看護のあり方が問われる今。
患者の“その人らしさ”を守る看護をどう貫くか――。
現場の管理者は、日々そのジレンマに向き合っているのではないでしょうか。
『臨床倫理 実践マニュアル』(ナーシングビジネス2025年秋季増刊号)の編著者・竹之内 沙弥香先生に、本書に込めた思いを伺いました。
現場の「迷い」や「もやもや」に寄り添う
臨床の現場では日々、患者や家族の思い、医療チームの判断、制度やリソースの制約のなかで、看護職が「どう支えるべきか」と悩み続けています。
“正解のない”問いに真摯に向き合い、誰もが「迷い」や「もやもや」を抱えながらも、目の前のケアの対象に誠実に関わろうと努力する。
その姿勢こそが、現場の看護を支えているのだと、私たちは信じています。
よくある事例の対応から職場づくりまで
本増刊号では、そうした看護現場で生じている倫理的ジレンマに光をあて、どのような支援や対話が可能かを、各領域の第一線でご活躍の先生方に、ケースを通して多角的にご執筆いただきました。
「身体拘束」「意思決定支援」「ACP の支援」「看取り」「子どもと親の意思決定」「多職種連携」など、看護実践において誰もが直面しうるテーマを取り上げてくださっています。
読み進める中で、読者の皆さまご自身が、職場の風土や支援体制を見つめ直し、スタッフの悩みに寄り添いながらともに考え、ともに成長していくための糧となればと願っています。
「倫理」は対話と関係性のなかで育つ
本誌では、「倫理」を難しいものとしてではなく、日々の実践に根ざした、対話と関係性のなかで育まれる営みとしてとらえ直そうと試みました。
執筆者の皆さまの温かく示唆に富む視点が随所ににじみ出ており、私自身も多くの学びをいただきました。
一人ひとりの看護のまなざしが、臨床倫理を“ 現場の力” へと変えていく――。
本増刊号が、読者の皆さまの日々の実践を支える一助となりましたら幸いです。
京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻 先端基盤看護科学講座 看護倫理学分野 准教授 竹之内 沙弥香
(本書「はじめに」より抜粋)
………………………………………………………
目 次
【第1章 臨床倫理の基礎を学ぶ】
■1 臨床倫理とは何か ―「患者にとっての最善」を考える力
■2 生命倫理の4原則 ―判断の助けになる枠組み
■3 いま、なぜ臨床倫理なのか ―看護現場の変化と求められる対応
【第2章 ケースで学ぶ 看護現場の倫理的ジレンマ対応策】
■ケース1 高齢者の身体的拘束をめぐる葛藤
■ケース2 意思決定支援と判断能力のゆらぎ
■ケース3 ACPをめぐる実践的課題
■ケース4 急性期・ICUでの生命維持治療の限界
■ケース5 在宅看護現場での高齢者の意思決定支援
■ケース6 こどもと親のはざまにおいて支える意思決定
■ケース7 精神科看護における倫理的まなざし
■ケース8 タスク・シフト/シェア時代の責任の所在
■ケース9 DX時代のテクノロジー導入と人間らしさ
【第3章 倫理観を醸成するための組織づくり】
■1 倫理的な組織文化を育てる ―組織風土とリーダーシップの役割
■2 現場の倫理的看護実践能力の底上げ
■3 倫理カンファレンスを活かす ―日常の実践とつなぐ工夫
■4 対話と心理的安全性 ―考えを表明できる関係性づくり
■5 多職種で育てる倫理の視点
■6 「倫理的な看護」を評価する ―教育・研修・振り返りの工夫
【コラム 臨床倫理を取り巻く最新のトピックを考察する】
■コラム1 安楽死をどう考えるか
■コラム2 日本におけるスピリチュアルケア
■コラム3 ゲノム医療・遺伝医療をめぐる倫理的な問題