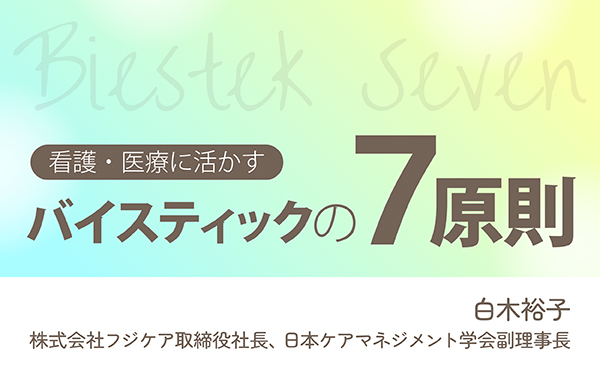第3回 意図的な感情表現の原則(バイスティックの7原則)
感情をひき出す意図的なはたらきかけ
相談援助のケースワークの場面においては、しばしばクライアント(利用者)が援助者に対して怒りや悲しみなどの感情をあらわにする場合があります。
その際に、援助者はそれを妨げたり、それから逃げたりせずに耳を傾け、むしろ感情をより表出できるように意図的にはたらきかけることが有意義となる場合があります。
なぜなら、クライアントは援助者の助けを借りて自分の感情をひき出してもらうことで、不安や緊張から解き放たれるとともに、自分自身のなかで迷い葛藤していた問題を整理することができるからです。
また、この「意図的な感情表現の原則」は組織内・チーム内などにおける人材育成にも活用できます。
認知症の妻を介護する夫の本心
私がケアマネジャーとして担当した事例を紹介します。
この事例では、認知症の妻を夫が一人で介護していました。以前は、自宅を訪問すると居間に招かれて話をしていましたが、妻の認知症の症状が進むにつれ、夫からは玄関先で不機嫌な対応をされることが多くなりました。
そこで、あえて妻の自宅での様子を見せてほしいとお願いして、居間に上げてもらうことで夫と話す機会をつくりました。
そのなかで、まず夫の日常について話を聞くことにしました。
それから、夫の日ごろの介護をねぎらうとともに、一般的な話題として男性は介護の悩みを抱え込んでしまう場合が多いことなどの話をしました。
夫は、自分はそのようなことはないと否定しましたが、話を続けるなかであえて夫の感情をひき出すようはたらきかけていくうちに、つい大きな声を出して妻に手を挙げそうになったことがあり、自宅で介護を続けたいが、このままではよくない状況になるのではないかと迷いがあると話してくれました。
クライアントの感情を引き出す面接技術
そこで、まずはいまの環境を大きく変えずに夫の負担を軽減するため、「通い、訪問、泊まり」を一体的に提供する小規模多機能型居宅介護サービスの利用を提案し、承諾してもらいました。
このように、クライアントの葛藤が推察される場面において、援助者が一歩踏み込んでクライアントの感情をひき出していくことは、問題をいっしょに整理していくうえでたいへん有効であり、看護・医療の現場においても活用できると考えます。
ただし、クライアントの属人的な要素もあって、これ以上感情をひき出すことが危ぶまれる場合は、ただちに方向転換を図ることも必要です。
援助者は面接技術や雰囲気づくりなどの技量の習得に努めるとともに、日ごろから土台となるクライアントとの信頼関係を醸成していくことが求められています。
初出:「透析ケア」2022年28巻3号より一部改変
白木裕子(しらき・ひろこ)
株式会社フジケア取締役社長
看護師、認定ケアマネジャー
日本ケアマネジメント学会副理事長
次回は「統制された情緒的関与の原則」についてお話しします。