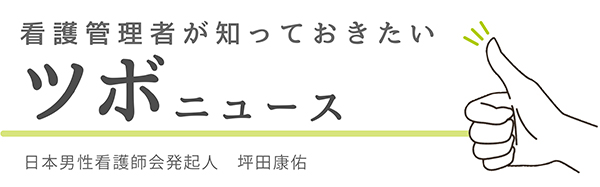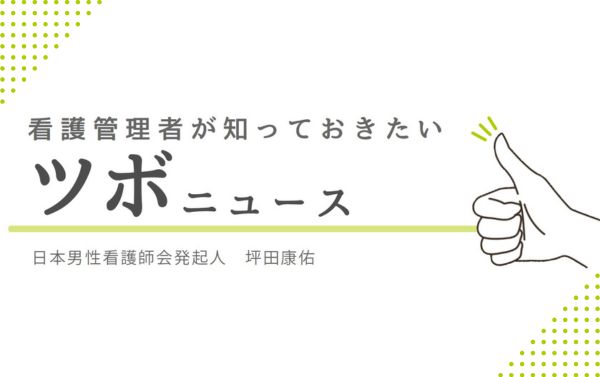看護管理者は日々多くの業務に目配り・気配りが必要です。国の施策や看護界を取り巻く状況、日々の働き方や組織づくりに関連した情報など、看護管理者が知っておきたい最新ニュースをご紹介します。
看護師の製品がグッドデザイン賞を受賞

今回は、看護師の新たな可能性を示す受賞ニュースをお届けします。
2024年10月16日、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する、2024年度 グッドデザイン賞の受賞者が発表されました。
5,000件を超える応募の中から、佛教大学保健医療技術学部看護学科の濱吉美穂さんの「わたしのいきかた手帳」も選出されました。
看護師の受賞は2年ぶりで、通算すると9件目、6人目となります。(参考までに、過去の看護師の同賞を表 1 に示します)。
表1 看護師のグッドデザイン賞受賞歴
| 2007 年 | 山本典子 | テープホルダー きるる |
| 真田弘美 | 床ずれ防止車椅子用 エアーセルクッション メディエア | |
| 2010 年 | 山本典子 | 点滴スタンド フィール |
| 2013 年 | 山本典子 | 点滴スタンド ディーボ |
| 2016 年 | 高丸慶 | 特別賞:退院支援 退院支援ナビ |
| 2017 年 | 麻生優恵 | 椅子 C-Fit-Chair(シーフィットチェア) [トライアングル・キュービック] |
| 2021 年 | 坪田康佑 | 三角巾・衣料品 ケアウィル |
| 2022 年 | 山本典子 | メジャー CocoMedi 乳幼児健診用メジャー |
| 2024 年 | 濱吉美穂 | ACP わたしのいきかた手帳 |
看護師視点のものづくり
日本では、診療報酬や介護報酬を含む社会保障費の増加が限界に達しており、看護師の給与を上げるためには、看護師が持つ知的財産を活用することが重要です。
看護師の視点を活かした「ものづくり」は、昨今では看護専門学校の授業にも取り入れられています。
また、看護大学も2006年の教育基本法改正(※)を受けて、専門的能力の育成や新たな知見の創造、社会への還元を推進し、看護大学でも産官学連携によるものづくりが増えています。
| (※)2006 年の教育基本法改正 2006年の教育基本法改正は、1947年の法律制定以来、実に約60年ぶりの大規模な見直しでした。この改正は、戦後の社会変化や新しい時代のニーズに対応するため、教育の基本理念や目標を現代に即したものに更新することを目的としています。とくに大学教育については、知識の習得だけでなく、社会に貢献する実践的な能力の育成や研究成果の活用に重点が置かれるようになりました。 改正された教育基本法第7条では、大学の役割として、高い教養と専門的能力の育成、新たな知見の創造、そしてその成果の社会還元が明記され、大学発スタートアップの促進が図られました。文部科学省は2014年から「グローバルアントレプレナー育成促進事業」を通じて、この動きを支援しています。看護大学での役割も変化し、産官学連携の促進が行われるようになりました。 |
今回の受賞は、大学所属の看護師が受賞するのが2007年以来、17年ぶりという快挙です。
看護師は生活支援や療養支援の現場で、課題を見つけ出し、解決策を創り出す能力に優れています。
看護師のものづくりは、看護教育の現場にとどまらず、病院発としても進んでいます。
たとえば、関西電力病院の看護師のアイデアから生まれた耳下腺がん・舌がん患者向けのカトラリーセットを販売する株式会社猫舌堂は、法人ごと関西電力グループから2023年小野薬品グループに合併・買収(M&A)されました。
看護師視点が生み出すアイデアの可能性
現在、社会保障費を通じた看護師の給与上昇には限界があります。
そこで注目すべきは、看護師独自の視点を活かした革新的な取り組みです。
たとえば、前出の関西電力病院から生まれたカトラリーセットの開発と事業化は、看護師の専門知識が社会に新たな価値をもたらした好例といえるでしょう。
看護管理者の皆さんには、スタッフの斬新なアイデアを積極的に支援し、育てる姿勢が求められています。
時には、それが新たな事業や収入源につながる可能性もあるのです。
今回のグッドデザイン賞受賞は、看護師の創造性と問題解決能力が社会から高く評価された証です。
この受賞を一つのモデルケースとして、私たち看護師の持つ潜在的な可能性にも目を向けていきましょう。
看護の専門性を活かしたイノベーションは、患者のQOL上だけでなく、看護師自身のキャリアや待遇改善にもつながる可能性を秘めています。
これからの看護界を担う皆さんの柔軟な発想と挑戦に、大いに期待が寄せられています。
2024 年グッドデザイン賞「わたしのいきかた手帳」
「看護師としての経験を活かし、デザインの力で医療と介護の未来を変える」。
今回、見事にグッドデザイン賞を受賞した濱吉美穂さんは、そんな思いを胸に、「わたしのいきかた手帳」を開発しました。
彼女の手帳は、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)を支える新しいツールとして注目されています。
濱吉さんは2009年、「わたしのいきかた手帳」の第一世代である「My Wish For Life」を開発しました。
しかし、この手帳は当初は利用者から「書く内容が固く、怖い」といったフィードバックを受けました。
そこで彼女は、「もっと気軽に、心のゆらぎを記載できるようにしたい」と、この手帳の進化を決意し、入院時にお薬手帳と一緒に持ち運べるような、生活に溶け込むデザインを目指して、デザイナーとともに開発を進めました。
「わたしのいきかた手帳」は、ACPを行うための重要なツールです。
自分の大切にしていることを考え、それを医療や介護の専門職者に伝えるための手帳として設計されています。
デザインのポイントは、手元に置いておきたくなるような質感と、自分のこれまでの生きざまやこれからの希望を段階的に考えられる仕掛けです。
今すぐに何かを決定しなくても、自分の気持ちの行方を見える化できるように工夫されています。
濱吉さんは、「生活の中にデザインがあることが大切」と語ります。
彼女の手帳は、単なる記録ツールではなく、人生の道しるべとしての役割を果たしています。
看護師としての視点とデザインの力を融合させたこの手帳は、医療と介護の現場に新しい風を吹き込むことでしょう。
看護師として働く私たちは、患者の抱える小さな課題を見つけることが得意です。
しかし、普段はいわゆる“ものづくり”に携わることはないため、初めから完成品を作り上げるのは難しいものです。
濱吉さんのように、着想を得てから患者のフィードバックを真摯に受け止め、製品を成長させていく姿勢は、素晴らしい成果を生む素敵な事例だと思います。
(わたしのいきかた手帳)
引用・参考文献
1) グッドデザイン賞HP.https://www.g-mark.org/gallery/winners/21140(2024年12月3日閲覧)
2) 小野薬品工業株式会社HP.https://www.ono-pharma.com/ja/news/20230630.html(2024年12月3日閲覧)
3) 佛教大学研究活動報.https://bukkyo-u-research.jp/research/research12/(2024年12月3日閲覧)

坪田康佑(つぼた・こうすけ)
慶應義塾大学看護医療学部卒。Canisius College(米国ニューヨーク州)卒/MBA 取得。無医地区に診療所や訪問看護ステーションを開業し、2019 年全事業売却。国家資格として看護師・保健師・国会議員政策担当秘書など、民間資格ではメディカルコーチ・M&A アドバイザーなどを持つ。
現在は国際医療福祉大学博士課程在籍、看護師図鑑(https://cango.blog/)を運営。
▼出典元:Nursing BUSINESS 2025年2月号